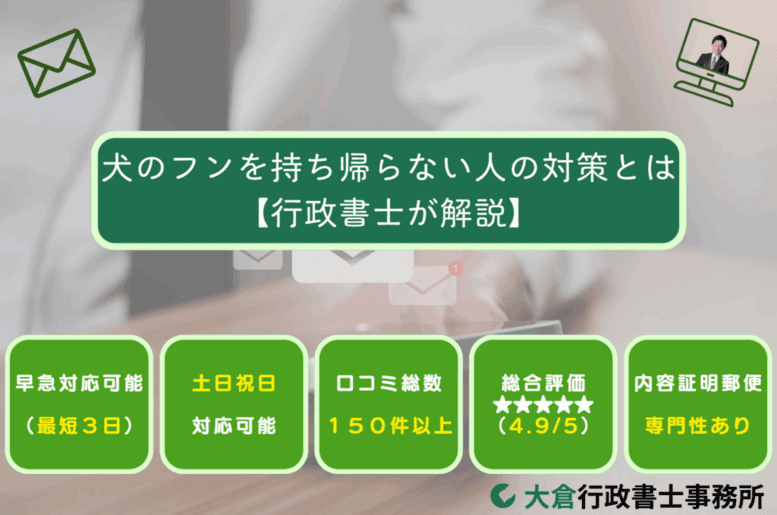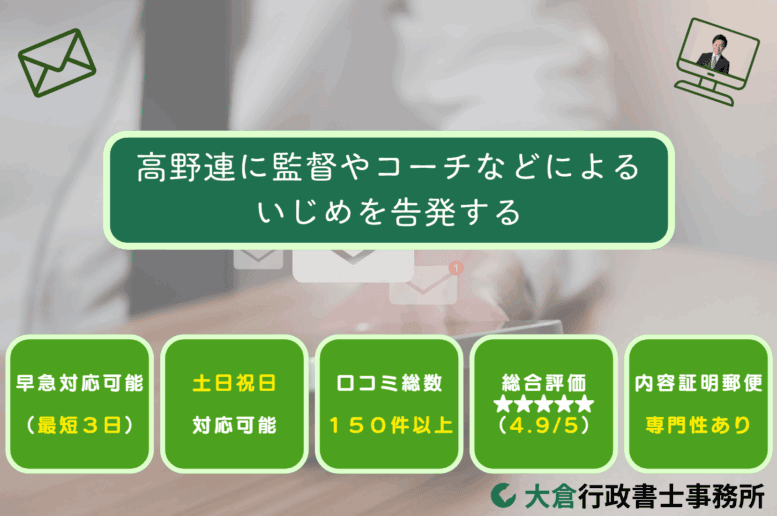静かな住宅街、公園、通学路、そんな日常の風景の中に、ぽつんと放置された犬のフン。誰かが処理せねばならず、不快感と衛生面の不安がつきまといます。多くの飼い主がマナーを守る一方で、一部のモラルなき飼い主によって、地域の環境や人間関係が損なわれている現実があります。
行政書士として数多くの生活トラブルに携わってきた立場から、こうした問題に法的な手段でアプローチする機会が増えています。特に悪質なフンの放置に対しては、内容証明郵便を用いた警告、さらには刑事告訴に至るケースも存在します。本記事では、犬のフンを持ち帰らない人の心理的背景や法的責任、そして実際にとるべき対策について詳しく解説し、トラブル解決の糸口を探ります。
犬のフンを持ち帰らない人の心理
![]()
犬のフンをそのまま放置する行為には、モラルの欠如だけでなく、いくつかの心理的な背景が隠れています。
ここでは、犬のフンを放置する人の典型的な三つの心理パターンに分けて解説します。
自分さえよければいいという利己的思考
犬の散歩は毎日の習慣であり、飼い主にとってはリフレッシュの時間でもあります。しかし、その一方で、フンの処理は手間がかかる不快な作業だと感じる人も多く、つい「この程度はいいだろう」と自己中心的な判断で放置してしまうことがあります。
こうした人は、周囲の衛生環境や他人への影響を顧みることなく、自分の手間や快適さを優先します。他人に見られていない状況であればなおさら、その場から何事もなかったかのように立ち去ってしまうケースが多いのです。このような利己的な思考は、日々の生活の中で無意識に強化される傾向があり、改善には外部からの注意喚起や制裁的な働きかけが必要となります。
誰かが片づけてくれるという他力本願
公園や歩道など、公共の場所でのフンの放置においては、「清掃員が後で処理するだろう」「他の誰かが気づいて掃除してくれるに違いない」といった他力本願的な心理が背景にあることも少なくありません。
このような考え方を持つ人は、自分がその行為の直接的な責任を負うべきという感覚が希薄であり、責任の所在を無意識に他人へ転嫁しています。地域住民の中には、黙って清掃している善意の方もおられますが、その善意に甘えて不作為を正当化するような行為は、長期的には地域全体のモラルの崩壊を招く恐れがあります。また、自分では“被害者が存在しない”と思い込んでいる点も問題であり、実際には不快感や精神的苦痛を与えていることに気づいていないことが多いのです。
少しくらい大丈夫という過小評価
「たった一回くらい」「このくらい誰も気にしない」といった軽い気持ちで放置する行動は、極めて危険です。これは典型的な過小評価の心理であり、自身の行動が周囲に与える影響を低く見積もってしまう傾向にあります。
最初は一度限りのつもりでも、その行動に対して誰からも指摘されなければ、「やっても大丈夫」という誤った成功体験として記憶され、次第にそれが習慣化していきます。また、他の飼い主が放置している場面を見かけたことがあれば、「みんなやっているから自分もいいだろう」という集団心理が働き、自制が効かなくなることもあります。こうして、個々の小さな過失が地域全体の環境悪化につながってしまうのです。
犬のフンを持ち帰らない人は犯罪なの?
![]()
犬のフンの放置行為は、「マナー違反」という言葉で片づけられることが多いものの、実際には法令に触れる可能性のある行為です。つまり、悪質なケースでは、明確に「違法」と判断され、行政処分や刑事責任を問われる場合もあります。以下に、代表的な三つの法的観点を整理します。
軽犯罪法違反
犬のフンを公共の場に放置した場合、軽犯罪法第1条第27号に規定される「汚物等の放置」に該当する可能性があります。この条文は、公共の場における清潔の保持や、公衆の快適な生活環境を守るために設けられた規定であり、違反した場合は拘留または科料といった処罰が科されます。
現実には警察による摘発が頻繁に行われるわけではありませんが、悪質な放置や繰り返しの違反が地域で問題視されるような場合には、警告や事情聴取の対象となることもあります。フンの放置を「たいしたことではない」と軽視していても、法的には明確に処罰の対象となる行為なのです。
地方自治体の条例違反
ほとんどの市区町村では、犬のフンの放置を防止するための独自の条例を設けています。代表的なものとしては大阪府の「動物の愛護及び管理に関する条例」や「ふん害防止条例」「環境美化条例」などがあり、これらの条例では飼い主に対して、排泄物を回収・持ち帰る義務を明文化しています。違反が確認された場合には、行政による注意・指導のほか、過料(行政罰)が科されることもあります。
たとえば「動物の愛護及び管理に関する条例」では、直接的に「フンの放置」に対して罰則を定めているわけではないものの、「飼養施設の内部及びその周辺を常に清潔にし、悪臭等の発生を防止すること」といった包括的な義務規定が設けられています。これにより、放置行為そのものを禁止する根拠として機能しています。
さらに、以下のように大阪府内の複数の市町村では、明確な過料規定を設けた上で、実効的な運用が行われています。
泉佐野市
泉佐野市では「環境美化推進条例」により、公共の場所での犬のフンの放置に対して1万円の過料を科すことが明記されています。平成25年度以降は巡視員制度を導入し、違反行為に対する監視と徴収の実施が継続的に行われています。(参考:路上喫煙、犬フン等の放置に対する過料徴収について/泉佐野市)
東大阪市
東大阪市では、条例の中で、「公共の場所で、飼い犬等を連れている者は、当該飼い犬等のふんを回収し、持ち帰らなければならない。」と規定されており、これに従わなかった場合には文書による処理命令の発出が可能です。さらに、命令に違反した場合には氏名・住所を公表することができると規定されており、強力な抑止措置が講じられています。(参考:犬となかよく暮らせる街に(犬の飼い方・マナー) | 東大阪市)
柏原市
柏原市など一部自治体では「ポイ捨て防止条例」によって、犬のフンの放置を禁止行為として定めており、違反者には最高2万円の過料を科すことが可能となっています。条例名に「犬」や「動物」が明示されていなくとも、廃棄物の不法投棄の一種として位置付け、取り締まり対象とする運用がなされています。(参考:ポイ捨て禁止条例 | 大阪府柏原市)
このように、地域によって条例の表現や適用方法、罰則の金額には差がありますが、いずれにしても「放置行為は違反」であることに変わりはありません。飼い主は、自分が住む自治体の条例を事前に確認しておくことが義務であり、うっかりや知らなかったでは済まされない時代になっています。特に悪質なケースでは、指導や過料だけでなく、住民からの通報や法的措置に発展することもあるため、モラルとルールを守る姿勢が一層求められているのです。
不法行為としての損害賠償
犬のフンを他人の敷地や玄関先などに放置した場合、その行為は民法709条に規定される不法行為に該当する可能性があります。被害者が精神的苦痛を受けたと認められた場合には、慰謝料請求が認められるケースもあります。たとえば、特定の住宅の前に何度もフンを放置されたことが原因で、精神的ストレスや生活の支障が生じた場合には、証拠をもとに損害賠償請求を行うことができます。
実際の裁判例(京都地裁平成3年1月24日判決)でも、犬の騒音や悪臭が原因で飼い主に対して数十万円程度の慰謝料が命じられた事例が報告されています。不法行為としての責任が認められるかどうかは、放置の頻度や悪質性、被害者の受けた損害の程度によりますが、放置された側にとっては日々の生活に多大な影響を及ぼす重大な問題であることは間違いありません。
犬のフンを持ち帰らない人に対する通知や通報は内容証明郵便で
![]()
犬のフンを放置する行為に対して、何度も注意をしても改善が見られない、あるいは誰がやっているか明確な場合には、毅然とした対応が必要です。その際、感情的な口頭での抗議ではなく、法的な手段によって冷静かつ確実に意思表示を行うことが、トラブルを最小限に抑えつつ相手に強い警告を与えるうえで効果的です。
その代表的な方法が、内容証明郵便の送付です。内容証明郵便とは、送った文書の内容と日付、宛先が証拠として公的に証明される手段であり、法律上の意思表示や警告を行う場面で広く活用されています。
内容証明郵便の効果
犬のフンを何度も同じ場所に放置しているような悪質な行為に対しては、日時や場所、頻度などの客観的な情報を記載した文書を送ることで、加害者に対して行動を改めるよう厳重に促すことができます。
このような文書を受け取った側は、自分の行動が「正式なかたちで記録され、監視されている」と強く自覚することとなり、心理的な抑止効果が期待できます。特に、匿名の苦情や口頭での注意には反応しないような相手でも、内容証明という形式で正式に送られた通知には無視できない重みを感じるため、行動の改善に結びつくことがあります。
再発防止と証拠化
内容証明郵便は、将来に備えた「証拠の蓄積」としても重要な意味を持ちます。相手が通知を無視して再び同様の行為を繰り返した場合、「一度正式に警告を受けていた」という事実が残っていれば、後の損害賠償請求や告訴の際に重要な証拠となります。
また、警察や自治体に通報する際にも、「すでに内容証明での警告を行っているが改善が見られない」と説明することで、行政の対応がより本格化しやすくなるというメリットもあります。単なる苦情ではなく、段階的に対応を進めているという証拠があることで、通報側の信用性も高まるのです。
行政書士のサポート体制
内容証明郵便を作成する際は、文面に法的な根拠や的確な事実の記載が求められるため、専門家である行政書士の支援を受けることが有効です。行政書士は、現場の状況や証拠写真、被害者の陳述などをもとに、法律に照らした適切な警告文を作成します。
依頼者の代理で内容証明を送付することもでき、相手方に対して「個人の苦情」ではなく「法的根拠を持った通知」であることを明確に伝えることが可能です。さらに、相手の反応がない、または行為がエスカレートした場合には、警察への相談や刑事告訴のための書類作成支援、損害賠償請求のための資料整理など、次の段階への法的サポートも提供できます。トラブルを円滑かつ冷静に処理するうえで、行政書士の役割は非常に重要です。
近隣トラブルに発展するケースと実例
犬のフンの放置は、単なる迷惑行為にとどまらず、時として深刻な近隣トラブルの原因となります。一度発生したフン害が、日常生活に与える心理的ストレスは想像以上に大きく、これが繰り返されることで怒りや不信感が募り、住民同士の関係が壊れてしまうことも珍しくありません。
たとえば、当事務所が対応したケースでは、東京都内のあるマンションでは、エントランス付近に何度もフンが放置される事案が発生し、防犯カメラの設置がされ、結果的に映像から加害者の特定には至りました。
その後、管理会社が注意したもののこれに応じなかったことで、最終的に当事務所に依頼し、内容証明郵便によって正式に抗議を行いました。この対応を受けて以降、フンの放置は止まりました。
このような事例に共通しているのは、「誰かが黙って我慢していれば済む」という考えが、かえってトラブルを大きくしてしまう点です。フン害に対して声を上げることは、決して“神経質な苦情”ではなく、地域の環境を守るための当然の行動です。しかし、注意をした側が逆に敵意を持たれるなど、感情のもつれから関係が悪化することもあるため、冷静かつ適切な手段を選ぶことが重要です。
このような背景から、行政書士による第三者的かつ法的なアプローチが有効です。関係性の悪化を最小限に抑えつつ、客観的事実に基づいた警告を行うことで、感情的な衝突を避けつつ問題の解決に導くことが可能です。
犬のフンの放置による自治体への通報
犬のフンの放置に対しては、先述のとおり個人での対応だけでなく、行政機関への通報という手段もあります。特に繰り返し行われる悪質なケースや、個人での対応が困難な場合には、自治体の力を借りることで状況を打開できる可能性があります。
多くの市区町村では、生活環境課、動物愛護センター、環境衛生課といった部門が、フン害に関する苦情や相談を受け付けています。通報があった場合、職員が現地調査を行ったり、注意喚起の看板やチラシを設置したりするなどの対応が行われることがあります。
特定のエリアで同様の苦情が複数寄せられている場合は、地域全体に向けて啓発活動を行うなど、より本格的な対応につながるケースもあります。
ただし、自治体による対応にも限界があります。まず、加害者が特定されていない場合には個別に警告することができず、あくまで一般的な啓発活動にとどまるケースが多いです。また、地方自治体の多くでは条例による規制が存在していても、実際には過料や罰則が適用されるまでには至らず、注意にとどまることがほとんどです。
このような事情から、自治体に通報する際は、できるだけ具体的な情報を添えることが大切です。日時、場所、フンの状況、飼い主の特徴、可能であれば写真などを添えて通報することで、職員が迅速に動きやすくなります。また、行政書士を通じて、証拠の整理や通報書面の作成を行うことで、より正式かつ説得力のある通報となり、自治体側も真剣に対応せざるを得なくなります。
犬のフンを持ち帰らない人に対する通知はお任せください
![]()
犬のフンの放置は、単なる迷惑行為では済まされません。繰り返されることで、精神的ストレスや近隣トラブルを引き起こし、被害者にとっては深刻な生活被害となります。とはいえ、相手との関係性や周囲への影響を考えると、「どう注意すればいいのか分からない」「直接のやり取りは避けたい」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そうした時こそ、行政書士の法的サポートをご活用ください。当事務所では、犬のフンを放置する加害者に対して、事実関係に基づいた丁寧かつ毅然とした内容証明郵便を作成・送付し、再発防止を促すサポートを行っています。また、証拠の整理や通報書類の作成支援も承っておりますので、自治体や警察への対応にも備えることができます。
特に次のようなお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
- 犬のフンを自宅前や敷地内に何度も放置されていて困っている
- 近所の飼い主に注意したいが、トラブルにならないか不安
- 管理会社や自治体に相談しても解決せず、次の手段を取りたい
- できるだけ冷静かつ法的に対応したいが、自分では文面が難しい
- 慰謝料請求や告訴も視野に入れて、法的な記録を残したい
「内容証明は敷居が高い」と思われるかもしれませんが、当事務所では一つ一つの事案に寄り添いながら、わかりやすく丁寧に対応いたします。まずは、被害の状況やお悩みをお聞かせください。法的な立場から、最適な対処法をご提案させていただきます。
犬のフンの放置は見過ごしてはいけない問題です。あなたの声が、地域の環境と秩序を守る第一歩になります。ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
手続の流れ
1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。
| ⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |
2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。
3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。
4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し(クーリングオフ等の場合には原則2日前後です。)ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)
5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。
6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。
【郵送書類】
- 内容証明郵便の謄本 計1通
- 配達証明書 計1通
- 領収書 計1通
- その他書類(名刺、アンケート等)
以上が大まかな手続の流れでございます。
ご依頼いただくメリット
下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。
メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。
メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。
メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。
行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。
メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)
しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。
ご依頼料金
| 業務内容 | 案件(受取方) | 基本料金 | 概要 |
| 内容証明郵便の 作成と差出 | 個人・法人 | 33,000円~ | 2,000文字から5,000文字程度の通知書を作成いたします。 |
| 内容証明郵便 トータルサポート | 〃 | 44,000円~ | 〃 |
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。
そのため、実施するサービスには自信をもっております。
![]()
内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。
![]()
【参考記事】
日本郵便株式会社 内容証明