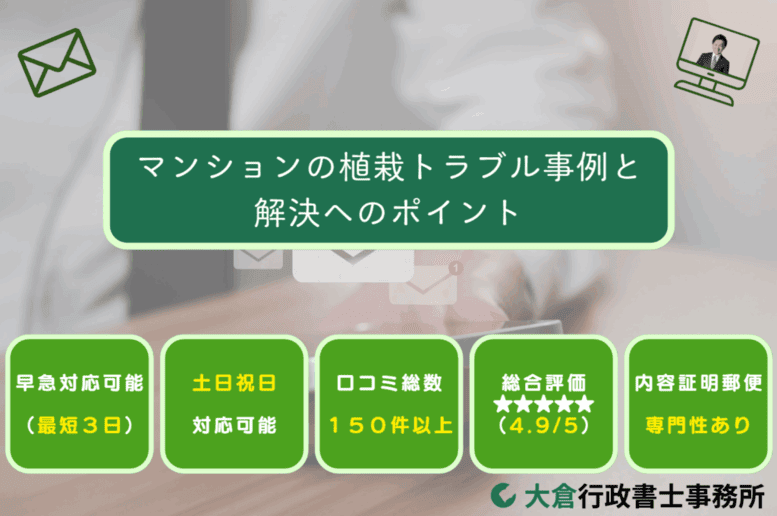マンションの敷地内やバルコニーでの植栽(植物の設置・栽培)を巡って、近隣住民同士や管理組合との間でトラブルが起きることがあります。植栽は本来生活に潤いを与えるものですが、管理や配慮が不十分だと迷惑行為と受け取られ、思わぬ紛争に発展することもあります。
本記事では、マンションにおける植栽トラブルのよくある事例と、その対処法・解決策について解説します。快適で安心な住環境を守るために、植栽に関するマナーとトラブル対応のポイントを確認しておきましょう。
マンションで起こりやすい植栽トラブルとは
![]()
マンションで起こりやすい植栽トラブルにはどのようなケースがあるのでしょうか。
植栽トラブルには様々なパターンがありますが、以下では代表的な事例をいくつか紹介します。
- 越境する樹木の枝
マンション敷地内やバルコニーの樹木が生長しすぎて、隣の敷地や下階のスペースにはみ出してしまうケースです。隣地へ生い茂った枝葉が越境し、日照を遮ったり落ち葉を落としたりして近隣に迷惑をかけることがあります。例えば下の階のベランダに上階から植木の枝が垂れ込んできたり、隣接する家の庭にマンションの木の枝が入り込むといった問題です。 - 落ち葉やゴミの飛散
ベランダや共用部で育てている植物の落ち葉が飛んで他の部屋のバルコニーや隣家の敷地に散乱するトラブルもあります。秋には大量の落ち葉が排水口を詰まらせたり、清掃の負担を強いることになりかねません。また植木鉢の土や枯葉が風で飛んで迷惑になる場合もあります。 - 水漏れ・湿害
ベランダガーデニングで大量に水やりをすると、鉢底から流れ出た水が下の階のベランダに滴り落ちることがあります。この水滴が洗濯物を濡らしたり、床面にシミを作ったりしてクレームになることがあります。また過剰な水遣りでコケやカビが発生し悪臭や害虫の原因となる場合も考えられます。 - 景観・日照・通風の妨げ
マンションの共有部分にある高木や生垣が伸びすぎて、一部の住戸の日当たりや眺望、風通しを妨げるケースもあります。特定の住民が「部屋が暗くなった」「風が通らない」と苦情を訴えることがあります。また逆に、管理組合が樹木を剪定・撤去した際に「お気に入りの木を勝手に減らされた」と不満を持つ住民が出るケースもあります。 - 共用部の無断占有
廊下やエントランスなど共用スペースに、住民が無断でプランターや鉢植えを置いてしまうこともトラブルの種です。共用部分は本来全住民のための空間であり私物化は禁止のはずですが、「ちょっと花を飾りたい」という善意から規約違反になっている場合があります。他の住民から見ると通行の邪魔になったり、管理が行き届かず枯れた植物が放置され景観を損ねたりといった問題につながります。
以上が典型的な植栽トラブルの例です。要するに、「自分のところの植物が他人に迷惑を及ぼす状態」になったとき、トラブルが顕在化します。では、こうした問題が起きた場合どのように対処すれば良いのでしょうか。
マンションで植栽トラブル発生!まずは話し合い
![]()
マンションの植栽トラブルが発生したら、いきなり法的手段に訴える前に当事者間の話し合いや管理組合・管理会社への相談で解決を図るのが基本です。まず、例えば隣の家の木の枝が自宅のバルコニーに越境してきたような場合、そのお隣さんに穏やかに声をかけてみるのが第一歩です。
「枝がこちらまで伸びてきているようなので、剪定をお願いできませんか?」といった具合に、冷静に依頼してみましょう。
相手も気付いていなかっただけで、言われて初めて状況を認識し、すぐに対応してくれるかもしれません。同じマンション内の住人同士であれば、管理組合や管理会社を仲介に入れる方法も有効です。マンションでは通常、管理組合が共有部分の植栽管理責任を負っています。(バルコニーは通常、共有部分とされています。)
賃貸マンションの場合は、貸主である大家や管理会社に相談します。例えば、隣室のベランダで大量の植物を育てていて水漏れや虫の発生に困っているなら、その旨を管理会社に伝え注意してもらいましょう。賃貸の大家は入居者に良好な環境を提供する義務がありますから、植栽による迷惑行為も放置すれば責任を問われ得ます。
管理会社経由で注意喚起してもらえれば、直接言いにくい苦情も伝えやすくなるでしょう。話し合いの際のポイントは、感情的にならず冷静に事実を伝えることです。植栽に愛着がある人にとっては指摘されると悲しいものですが、だからと言って我慢できない被害が出ているなら率直に伝えるべきです。
写真を見せたり実際に現場を確認してもらったりすると、客観的に状況を共有できます。お互い譲れる点・譲れない点を整理し、落とし所を探りましょう。
法律は何と言っている?越境する樹木への対処(民法233条)
![]()
植栽トラブルの中でも隣地との境界を越えて枝が伸びてくる問題は、法律上のルールが定められています。
民法第233条では、隣の土地から越境してきた竹木の枝の処理について規定があります。
民法233条では、隣地から越境した枝について一定の手順を踏めば所有者の承諾なく切除できることが明文化されています。ただし無秩序に切って良いわけではなく、また民法第233条による当事者は「土地の所有者」とされている点には注意が必要です。まずは以下のような段取りが求められます。
- 所有者に剪定を依頼する
隣の木の所有者が判明している場合(隣家が居住中で話し合える場合)は、直接または書面で「枝を切って欲しい」旨を伝えます。これが催告と呼ばれる手続きで、その依頼をした日から通常2週間程度の期間を相手に与えます。まずは穏便にお願いし、それでも応じてもらえない場合に次のステップへ進みます。 - 内容証明郵便で正式に通知する
依頼に相手が応じない場合、内容証明郵便などで改めて枝の切除を求める通知を送ります。これにより「○月○日までに越境部分の枝を切ってください」と公式に催告します。内容証明であれば相手にプレッシャーを与える効果もあり、証拠としても残ります。 - 越境部分の枝を切除する
上記の通知をしてもなお相手が対応しない場合、越境している部分に限ってこちらで枝を切り落とすことが認められます。必要な場合は隣地に立ち入っての作業も許されます。(民法第209条第1項)
以上が法律に定められた越境枝への対処手順です。要は「まずお願い、それでもダメなら内容証明で通知、最後は自分で切る」という流れになります。マンションの場合、隣地というのが同じ敷地内の別住戸なのか、マンション敷地と外部の戸建て住宅なのかで状況は異なります。
いずれにせよ、勝手に他人の木を切るのはトラブルを招くので、必ず事前に正式な依頼をすることが重要です。もしマンションの敷地内植栽が外部の家に迷惑をかけているなら、管理組合が主体となってこの手順に沿い対応すべきでしょう。
| 第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り) 1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。 3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 ①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 ②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 ③急迫の事情があるとき。 4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 |
| 第209条(隣地の使用) 1 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。 ① 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕 ② 境界標の調査又は境界に関する測量 ③ 第233条第3項の規定による枝の切取り 以下、省略 |
内容証明郵便による要求書で問題解決を促す
![]()
上記のように、植栽トラブルでも内容証明郵便は強力な武器となります。例えば「何度頼んでも隣の○○さんがベランダの植木を撤去してくれない」といった場合、行政書士などに依頼して植栽の迷惑行為停止を求める通知書を内容証明で送付してもらうことが考えられます。
内容証明郵便とは
「誰が・誰に・いつ・どのような内容の文書を送付したのか」を郵便局が証明してくれる制度であり、相手に対して正式な意思表示を行う際に用いられる重要な手段です。
通常の手紙では、「そんな通知は受け取っていない」「そんな内容は書かれていなかった」と言い逃れされるリスクがありますが、内容証明であれば送付の事実とその文面が公的に証明されるため、万が一の法的トラブルに備えて証拠力を確保することができます。
マンションの植栽トラブルと内容証明郵便
特にマンションの植栽トラブルのように、これまで口頭や通常郵便によるお願いが無視されてきた場合には、内容証明による通知が極めて効果的です。
これにより、相手に対して「これ以上放置すれば法的措置も辞さない」という強い姿勢を明確に伝えることができ、当事者としての本気度や問題の深刻さがしっかりと伝わるため、相手の対応を促すきっかけとなります。
実際に、繰り返しの迷惑行為が内容証明一通で収まったという例も少なくありません。また、内容証明での通知は将来的に調停や訴訟に発展した場合でも、「事前にきちんと催告した」という事実の裏付けとなり、非常に強力な証拠として活用することが可能です。単なる苦情やお願いにとどまらず、法的観点から相手に明確な要求を突きつける手段として、内容証明郵便はトラブル初期対応の切り札となる存在です。
通知書には「○月○日までに越境している枝を切除してください。期限までに対応なき場合は、民法233条に基づき当方にて切除いたします。」等といった内容を盛り込むことになるでしょう。これにより相手に自主的な対応を促し、場合によっては費用負担の覚悟もさせるわけです。
また、管理組合宛てに出す方法もあります。例えば管理組合が共用部植栽の適切な管理を怠っており被害を被っている場合、「早急な剪定等の対応を要求します」という内容証明を管理人宛てに送れば、組合全体へのプレッシャーとなります。いずれの場合も、内容証明郵便は証拠作りと相手への心理的圧力に効果絶大ですが、最終手段ゆえに関係修復は難しくなる点は留意しましょう。
専門家に相談して円満解決を目指そう
植栽トラブルは感情的なもつれになりがちで、当事者同士では解決が難しいケースもあります。そうした際は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
行政書士であれば、必要な場合には内容証明郵便による通知書や合意書作成といった形で問題解決に向けたサポートを提供してくれます。
第三者が介入することで感情的なぶつかり合いを避け、冷静な話し合いによる解決の糸口が見えてくることもあります。当事務所でも、マンションの植栽トラブルに関するご相談を承っております。全国対応で、内容証明郵便による加害行為停止通知書の作成代行を行っておりますので、遠方の方でもお気軽にお問い合わせください。専門家の立場から適切なアドバイスと書面作成を通じて、円満解決へのお手伝いをさせていただきます。大切な住環境を守るために、ひとりで悩まずぜひご相談ください。信頼できる行政書士が、丁寧かつ迅速に問題解決に向けてサポートいたします。
マンションの植栽トラブルでお困りではありませんか?
内容証明郵便による正式な通知書作成は、当事務所にお任せください
マンション内での「越境する枝」「ベランダの植木からの水漏れ」「落ち葉の飛散」「共用部の無断占有」など、植栽をめぐるトラブルは、住民間の人間関係にも深く関わるため、単なる苦情では済まされない深刻な問題に発展することがあります。
当事者同士の話し合いで解決できれば理想ですが、「注意しても繰り返される」「管理会社が動いてくれない」「相手と直接話すのは怖い」といったご相談をよくいただきます。
そうしたときは、行政書士による内容証明郵便の送付が有効です。民法に基づいた正確な根拠と、相手に対する心理的圧力・改善への促しを、書面という法的手段で伝えることができます。当事務所では、次のような植栽トラブルに対応可能です。
- 隣のバルコニーから越境してくる樹木の枝葉の剪定要求
- 上階からの鉢植え水漏れ、下階への被害の是正要求
- 管理組合に対して日照・景観被害への対応を求める通知
- ベランダガーデニングによる害虫・悪臭トラブルの警告書送付
- 共用部に放置された鉢植えの撤去要請
すべての通知書は、法的根拠・事実関係・経緯を丁寧に整理し、万一の裁判や調停時にも証拠として活用できる内容で構成いたします。また、内容証明郵便にとどまらず、再発防止のための合意書作成や契約書の整備など、行政書士としての視点から中長期的な問題解決をご提案できます。
手続の流れ
1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせによりマンションの植栽トラブルによる内容証明郵便の通知を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。
| ⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |
2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。
3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。
4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成しご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)
5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。
6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。
【郵送書類】
・内容証明郵便の謄本 計1通
・配達証明書 計1通
・領収書 計1通
・その他書類(名刺、アンケート等)
以上が大まかな手続の流れでございます。
ご依頼いただくメリット
下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。
メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。
メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。
メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。
メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。
ご依頼料金
| 業務内容 | 案件(受取方) | 基本料金 | 概要 |
| 内容証明郵便の 作成と差出 | 個人・法人 | 33,000円~ | 2,000文字から5,000文字程度の通知書を作成いたします。 |
| 内容証明郵便 トータルサポート | 〃 | 44,000円~ | 〃 |
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。そのため、実施するサービスには自信をもっております。
![]()
内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。
![]()
【参考】
>日本郵便株式会社 内容証明