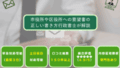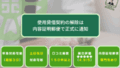弁護士に依頼したものの「断られてしまった…」という経験はありませんか。大きな不安や失望を感じるかもしれません。しかし「弁護士に断られたら終わり」ではありません。
実は、ケースによっては行政書士という専門家がサポートできる可能性があります。行政書士は契約書や内容証明郵便の作成など法律関連の書類作成を業とする国家資格者で、身近な法務の相談役として活躍しています。
この記事では、弁護士が依頼を断る理由から、行政書士が担える役割、そして行政書士でも難しい場合の対処法まで詳しく解説します。弁護士と行政書士それぞれの役割を正しく理解し、状況に応じた賢い専門家の活用方法を見つけていきましょう。
弁護士が依頼を断る理由とは
![]()
まず最初に、なぜ弁護士が依頼を断ることがあるのか、その一般的な理由を確認しましょう。実は弁護士には法律上、「必ず依頼を受けなければならない」という受任義務はありません。弁護士もビジネスとして業務を行っているため、依頼を選ぶ権利があるのです。
依頼を断られてしまった背景には様々な事情が考えられますが、大きく分けて以下のような理由が挙げられます。
低単価案件を避ける弁護士の実情
現実問題として、依頼の規模や金額が小さい案件は弁護士に敬遠されがちです。弁護士に依頼すると相談料・着手金・報酬金など費用がかかりますが、もしその費用が依頼によって得られる利益を上回ってしまうような場合、弁護士は依頼を受けても「費用倒れ」になってしまいます。
弁護士も時間と労力を費やす以上、採算が取れない案件は避けたいのが本音です。「勝ってもペイしない(利益にならない)事件」は特別な事情がない限り受任しないという弁護士も実際にいます。例えば、取り戻せるお金がごく少額な紛争や、手間の割に報酬見込みが低い依頼は、どうしても後回しにされやすいのです。
訴訟に発展しない案件の扱い
裁判沙汰に発展しないような案件も、弁護士が断るケースがあります。たとえば「とりあえず内容証明郵便で警告してほしいが、裁判までは考えていない」というような依頼です。
弁護士から見ると、訴訟に至らない事案では自分の専門的関与が限定的で、依頼者がその後本格的な法的手続きを取らなければ問題解決に至らない可能性があります。つまり「手紙を出すだけ出して終わり」といった仕事になりかねず、弁護士としては積極的に受任しづらいのです。
こうしたケースでは、弁護士より費用が抑えられる他の手段(後述する行政書士の活用など)を依頼者に勧める弁護士もいるでしょう。また、トラブル自体は小さく当事者同士の話し合いで解決できそうな場合も、「弁護士が出るまでもない」と判断され依頼を断られることがあります。
専門分野外・リスク回避の理由
弁護士にも得意分野・不得意分野があります。専門外の案件は十分な知識や経験がないため、「他の専門の先生に任せた方が良い」と判断して断ることがあります。
例えば、普段は離婚問題を扱わない弁護士が複雑な相続案件を相談された場合などです。また、勝ち目が薄い案件や依頼者と十分な信頼関係が築けない案件も断られる傾向にあります。
弁護士は自分の力量や倫理観に照らし、「リスクが高い」「引き受けても解決が難しい」と感じれば受任を見送ることがあるのです。さらに、利益相反(利害の衝突)にあたる場合は法律上受けることができません。
例えば、既に相手方の相談を過去に受けていた等のケースでは依頼を断らざるを得ません。このように、弁護士が依頼を断るのにはさまざまな正当な理由が存在します。
| 豆知識:弁護士には依頼の受任義務が法律上ありません。一方で行政書士や司法書士には、それぞれ行政書士法第11条、司法書士法第21条で「正当な事由がなければ依頼を拒んではならない」という規定があります。 |
もっとも、行政書士や司法書士の場合、受けられる依頼の範囲自体が法律で限定されています(後述)。弁護士には受任義務はありませんが、弁護士法第72条により非弁行為(無資格者による法律事務)を禁止する規定があり、依頼者の利益を守る仕組みになっています。
| 行政書士法第11条(依頼に応ずる義務) 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。 |
弁護士に断られたあとにできること
![]()
弁護士に依頼を断られてしまっても、まだ打つ手はあります。大切なのは「なぜ断られたのか」を踏まえて次の行動を考えることです。弁護士に断られる理由の多くは前述のとおりですが、それは必ずしもあなたの案件が解決不能という意味ではありません。
訴訟にならない、比較的軽微なトラブルであれば、別の専門家の力を借りることで解決への道筋が見えてくることもあります。ここでは、弁護士に断られた後に検討すべき選択肢として行政書士の活用について紹介します。さらに、行政書士に依頼する際に知っておきたいポイントも見ていきましょう。
行政書士という選択肢
行政書士とは、法律に基づいて各種書類の作成や手続代理を行う国家資格者です。具体的には、官公署(役所など)に提出する許認可申請書類の代理申請や、契約書など権利義務に関する文書の作成を業務としています。
一般に行政書士は「街の法律家」などとも呼ばれ、弁護士ほど紛争解決に踏み込まないものの、書類作成と手続きのプロフェッショナルとして市民に身近な法務サービスを提供しています。
弁護士に断られた案件でも、訴訟にならない範囲の手続きや書面作成であれば行政書士が対応できる場合があります。たとえば「内容証明郵便で相手に通知書を送りたい」「契約書をきちんと作成したい」といったニーズは、行政書士の得意分野です。
行政書士は全国に多数おり、相談しやすい雰囲気の事務所も多いので、弁護士に依頼できず困ったときは一度行政書士への依頼を検討してみましょう。
👇当事務所へのご相談もご検討ください👇
LINE追加は→こちら
行政書士が対応できる案件の特徴
行政書士が得意とするのは、書類作成中心の業務です。争いになっていない事案や、将来の紛争を予防するための書面作成などが典型例です。実際、行政書士が作成できる書類は1万種類以上とも言われ、契約書・内容証明郵便・示談書や離婚協議書といった民事に関する書類の作成や相談も業務範囲に含まれます。
ポイントは、「紛争性のない」あるいは「裁判外で完結する」案件であることです。たとえば相手と合意が取れている内容を文書にまとめるケースや、役所に提出する書類の作成など、トラブルの予防や手続き代行が行政書士のフィールドです。
逆に言えば、争いが顕在化しているケースや法的主張が絡む案件は行政書士の扱える範囲ではありません(この点は後述します)。行政書士に相談すべきか迷うときは、その案件が「書類作成メインで解決を図れるものか」「相手との直接交渉や訴訟を要しないものか」を一つの判断材料にするとよいでしょう。
依頼前に確認すべきポイント
行政書士に依頼しようと決めたら、事前にいくつか確認しておきたい事項があります。まず依頼内容が行政書士の業務範囲に収まっているかを確認しましょう。行政書士はできることとできないことが法律で決まっており、依頼したい業務が弁護士の領域に及ぶ場合、受任してもらえないか違法行為となってしまいます。
たとえば「相手に損害賠償を請求したいので、代理で交渉してほしい」という依頼は、行政書士の業務範囲を超えるため対応できません。一方で、「損害賠償請求の内容証明を本人名義で送りたいので、その文面を作成してほしい」という依頼であれば、事件性がなく、行政書士が対応可能です。
微妙なラインの案件もあるため、依頼前の相談時にその行政書士が扱える内容かを正直に話し、確認することが大切です。また、行政書士ごとに得意分野がありますので、あなたの案件内容(例えば相続、離婚、金銭貸し借りなど)に実績のある行政書士を選ぶと安心です。
最後に費用面も事前に確認しましょう。行政書士は弁護士に比べて報酬が低めと言われますが、業務内容によって費用体系が異なります。見積もりや料金表を確認し、納得した上で依頼を進めてください。
行政書士が対応できる具体的な業務例
![]()
ここでは、行政書士が弁護士の代わりに対応可能な具体的事例を紹介します。「弁護士に頼むほどではないけれど、自分だけでは不安…」という場面で、行政書士がどのように力になれるのかイメージしてみましょう。行政書士は前述のとおり書類作成のプロです。
単発の書類作成から相談支援まで、幅広い書類作成・相談業務を通じて私たちをサポートしてくれます。以下に代表的な例を挙げます。
単発の書類作成業務(契約書、示談書など)
契約書の作成は行政書士が得意とする業務の一つです。ビジネス契約から個人間の取り決めまで、内容に沿った契約書を一から作成してもらえます。弁護士に契約書作成を依頼すると高額になりがちですが、行政書士であれば比較的リーズナブルにお願いできることが多いでしょう。
特に単発の書面作成だけで完結する案件(例:貸し借りの念書、金銭消費貸借契約書、離婚の合意書、示談書など)は、行政書士への依頼に向いています。行政書士は法律知識を活かしつつ、当事者間で合意した内容を適切な文書にまとめることができます。
実際に行政書士の扱う典型的な権利義務書類として契約書や離婚協議書、示談書などが挙げられており、内容についての相談にも応じてもらえます。重要な契約や合意事項は口頭ではなく書面で残すことがリスクヘッジになります。
弁護士に頼むほど複雑な法律判断を要さない場合、行政書士を活用して必要十分な契約書類を整備すると良いでしょう。
権利主張を伴わない通知書・内容証明作成
相手に何らかの通知や意思表示をする必要がある場合、内容証明郵便(郵便局が文書の内容と発送事実を証明する郵便)を利用すると効果的です。例えば、「これ以上迷惑行為をやめてほしい」という警告や、「○月○日までに支払いがなければ契約を解除します」という通知を送りたい場合です。
弁護士が関与するケースでは、代理人弁護士名で内容証明を送ることもありますが、行政書士でも内容証明文面の作成代行が可能です。
そのため、相手に事実を通知したり自分の意向を伝えたりする書簡であれば行政書士がプロの文章作成者としてサポートできます。実際、「内容証明郵便での通知業務」は行政書士の業務範囲に含まれており、多くの行政書士事務所が提供しているサービスです。
例えば貸金の返済請求や契約解除の意思表示など、将来裁判になる可能性がゼロとは言えない微妙なケースもありますが、その段階ではあくまで紛争予防のための文書作成として行政書士が関与できます。
ただ、相手がそれに応じなかった場合は裁判等に移行せざるを得ず、その際は弁護士の出番となります。まずは内容証明でプレッシャーをかけてみたいといった場合、行政書士に相談してみる価値はあるでしょう。
👇当事務所へのご相談もご検討ください👇
LINE追加は→こちら
相談・文書サポートでの活用方法
行政書士は書類作成だけでなく、その作成過程での相談役にもなってくれます。行政書士法上、行政書士は「書類作成に付随する相談業務」も行えるとされています。例えば、「自分で作成した契約書の内容が適切か確認してほしい」「相手に提出する書面を自分で書いてみたので添削してほしい」といった依頼も可能です。
「どのような内容を書けば角が立たないか」「法律用語でどう表現すればよいか」など、実務を知る行政書士ならではの視点で教えてもらえるでしょう。また、当事務所を含め行政書士事務所の中には無料相談会や文書作成教室のような形で市民向けにサポートを提供しているところもあります。
弁護士に依頼するほどではないけれど専門家のチェックが欲しい、という場面で行政書士を活用すれば、自力解決と専門知識の両立が図れます。
行政書士でも対応できない場合とその対処法
![]()
行政書士は便利な存在ですが、全ての法律トラブルを解決できるわけではありません。法律上、行政書士の業務には明確な限界があります。
ここでは行政書士に依頼できないケースと、その場合に取るべき対処法について説明します。
「行政書士にお願いすれば何でも代わりにやってくれる」と誤解してしまうと、かえって問題がこじれる恐れもあります。行政書士の権限の範囲を正しく理解し、必要に応じて他の専門家への切り替えを検討しましょう。
弁護士法第72条による制約とは
行政書士の業務を語る上で避けて通れないのが、弁護士法第72条の存在です。この条文は非弁行為の禁止規定で、簡単に言うと「弁護士でない者が、報酬を得る目的で他人の法律事件に関する法律事務を業として行うこと」を禁じています。
ここでいう「法律事件に関する法律事務」とは、訴訟や調停、不服申立てといった公に争いとなっている事案や、それに準ずる紛争性のある業務を指します。言い換えれば、紛争性のある案件に立ち入って法律業務を行うことは、弁護士以外には許されないということです。
行政書士は行政書士法という法律で一部の法律事務(書類作成等)が特別に認められている資格ですが、それも「事件性のない業務」に限られるとの解釈がされています。弁護士法72条に違反すると行政書士であっても刑事罰の対象となり得ます。したがって行政書士は、自身の業務が72条に抵触しないよう常に注意を払っているのです。
| 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 |
行政書士に依頼できないケースの具体例
弁護士法72条との関係から、行政書士には依頼できない(行政書士が対応できない)具体的ケースとして以下のようなものがあります。
相手との交渉や代理行為を伴う依頼
たとえば「債権者との示談交渉を代わりにやってほしい」「相手に慰謝料を請求してほしい」というような代理人としての交渉・請求行為は行政書士にはできません。
交渉は典型的な法律事務であり、当事者間に争いがある状況ですから、弁護士でなければ扱えないのです。行政書士がこれを行えば非弁行為に該当します。
裁判所に提出する書類の作成
訴状や答弁書など裁判所提出書類の作成は法律上司法書士や弁護士の業務範囲であり、行政書士は行えません。たとえ書面作成だけであっても、それが裁判手続きに関与するものであれば事件性があるとみなされます。
したがって「自分で訴訟を起こしたいので訴状を書いてほしい」という依頼も行政書士にはできません。※司法書士であれば簡易裁判所管轄(訴額140万円以下)の訴状作成代理など一部可能な場合がありますが、行政書士は不可です。
紛争性の高い法律相談
行政書士は「書類作成に関する相談」はできますが、法律そのものの相談、特に揉め事に関する具体的な解決策の相談には応じられません。例えば「遺産分割でもめているがどうしたら良いか」といった相談は法律相談そのものなので行政書士の守備範囲外です。
実際、他の相続人と揉めている状況では行政書士は一切業務を行えないとの指摘もあります。このような相談は弁護士の領域になります。
以上のように、相手のあるトラブルで争いが表面化しているケースや法的請求・主張を代理人として行う行為は行政書士には頼めないと覚えておきましょう。「それはできません」と断られて初めて気付くのでは時間のロスになります。早い段階で行政書士では無理だとわかった場合は、迷わず別の方法を検討することが重要です。
再度弁護士に相談する際のポイント(若手・個人事務所が狙い目)
行政書士でも対応できない場合、最終的には再度弁護士に相談する必要があります。前回依頼を断られたからといって尻込みする必要はありません。同じ事務所にこだわらず、視点を変えて新たな弁護士を探してみましょう。
その際のポイントとして、若手の弁護士や個人で開業している弁護士を当たってみることをおすすめします。大手の法律事務所やベテラン弁護士は扱う案件も大規模になりがちで、どうしても小さな案件には手が回らないことがあります。
一方、経験年数の浅い弁護士や町の個人事務所の弁護士は、新規顧客を求めていたり地域の身近なトラブル解決に力を入れていたりするため、比較的小規模な案件でも親身に対応してくれることがあります。実際、一度は他で断られた依頼でも引き受けてもらえた例は珍しくありません。
探し方としては、弁護士紹介サイトや各都道府県の弁護士会の相談窓口を利用すると便利です。また、複数の弁護士に当たってみるのも有効です。相性や方針は弁護士によって様々ですので、セカンドオピニオン的に複数に相談してみると受任してくれる弁護士が見つかる可能性が高まります。
また、経済的な事情で弁護士費用の支払いが難しい場合は「法テラス(日本司法支援センター)」の利用も検討しましょう。法テラスは国が設立した公的機関で、一定の収入基準を満たす方であれば無料の法律相談や、弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)を利用できます。
特に、「弁護士費用が高くて依頼を断念した」「相談先が見つからない」といった場合には、法テラスが心強い味方になります。
弁護士に断られたらどうする?-結論・まとめ
![]()
弁護士に依頼を断られても、決して行き止まりではありません。今回見てきたように、訴訟に至らないような案件であれば行政書士があなたの力になれる場合があります。行政書士は契約書・内容証明・示談書など書類作成のプロとして活躍し、法律トラブルの予防や解決の一端を担っています。
一方で、行政書士では対応しきれない紛争性の高い案件や法的交渉が必要な場面では、改めて弁護士の助力が必要になります。大切なのは、弁護士と行政書士それぞれの役割を正しく理解し、適材適所で使い分けることです。
弁護士には弁護士の、行政書士には行政書士の強みがあります。本記事を参考に、「弁護士に断られたらどうすれば…」という不安を乗り越え、ぜひ次の一歩を踏み出してください。専門家を上手に活用することで、あなたの抱える問題にもきっと解決への道筋が見えてくるはずです。安心して、前向きに取り組んでいきましょう。
内容証明郵便や契約書等の作成はお任せください
当事務所では、弁護士に依頼するほどではないけれど、法的にきちんと形を整えておきたいという方のために、次のような書類作成・相談を幅広くサポートしています。
- 各種契約書(売買・金銭消費貸借・離婚・示談など)の作成
- 内容証明郵便・通知書の作成・送付サポート
- 誓約書・合意書・念書の作成
- 行政手続・許認可申請書類の作成・代理提出
法律の専門知識をもとに、依頼者様の意向を丁寧にヒアリングし、実際に使える文書として仕上げます。弁護士に断られてお困りの方も、まずはお気軽にご相談ください。
下記は内容証明郵便の場合の流れや料金となります。
手続の流れ
1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。
| ⑴ お電話によるご相談は→0743-83-2162(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |
2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。
3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。
4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し(クーリングオフ等の場合には原則2日前後です。)ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)
5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。
6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。
【郵送書類】
- 内容証明郵便の謄本 計1通
- 配達証明書 計1通
- 領収書 計1通
- その他書類(名刺、アンケート等)
以上が大まかな手続の流れでございます。
ご依頼いただくメリット
下記には、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。
メリット1 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。
メリット2 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。
行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができます。
メリット3 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)
しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。
ご依頼料金
下記の料金には、当事務所の記名費用を含んでおります。 (一部のサービスでは記名できない場合がございます。) 内容証明の郵送費等は別途かかります。
| 業務内容 | 案件(受取方) | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 内容証明の作成と差出 | 定型外文面(個人・法人) | 33,000円~ | 1,000文字から4,000文字(最大)程度の内容文書を作成します。 |
| 内容証明トータルサポート | サービスによってご利用いただけます。 | 44,000円~ | 〃 |
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。
そのため、実施するサービスには自信をもっております。
![]()
内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。なお、金額によってページ数は異なります。
![]()
【参考記事】
日本郵便株式会社 内容証明