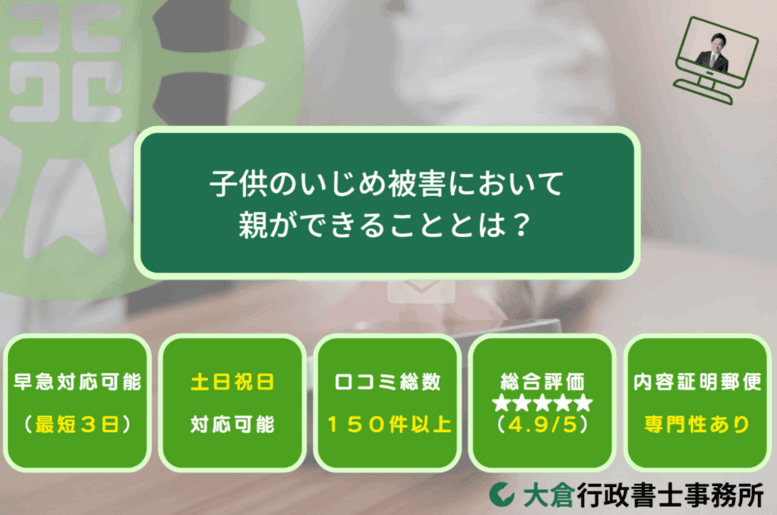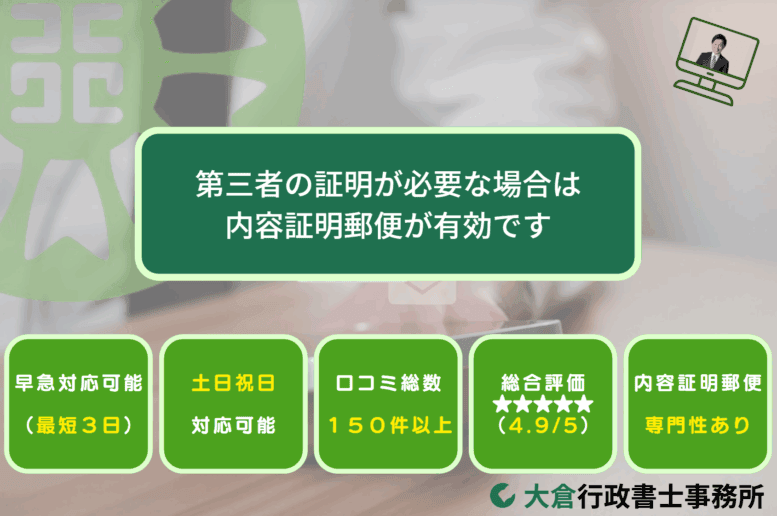子供が学校でいじめを受けていると知ったとき、親は大きなショックを受け、不安や怒りで「どうすれば良いのか分からない」と混乱してしまうかもしれません。
最近では、いじめが原因で不登校や自殺など深刻な結果を招くケースも報道されており、決して他人事ではありません。いじめに直面した際に親ができることは決して少なくありません。適切な対応を取ることで、子供の心身を守り、いじめの解決に近づけることができます。
本記事では、小学生・中学生・高校生といったお子さんのいじめ被害において、親が取るべき対応策について詳しく解説します。親御さんが今抱えている悩みを少しでも和らげ、具体的な一歩を踏み出す助けになれば幸いです。
子供のいじめ発覚時に親ができることや取るべき対応
![]()
このトピックでは、子供がいじめに遭っていることが分かった際に、親が最初に行うべき基本的な対応について説明します。
慌てず冷静になることから始め、子供の話をしっかり聞いて状況を把握し、今後の対策の基礎を築くステップです。
最初の対応次第で、その後の解決に向けた流れが大きく変わります。
まず親が冷静になる
大切な我が子がいじめられていると知れば、親として怒りや悲しみで感情的になってしまいがちです。しかし、ここで親が感情的に振る舞うと、子供はさらに不安を感じてしまう可能性があります。
まずは深呼吸をして気持ちを落ち着け、冷静に状況を受け止めましょう。親が取り乱してしまうと子供も動揺して本当のことを話せなくなったり、適切な対応が後手に回ったりしかねません。
例えば、怒りのあまり加害児童やその親に直接連絡したり学校に乗り込んだりすると、かえって問題がこじれる恐れもあります。心を落ち着かせることで、今後取るべき行動を理性的に判断することができます。
子供の話をじっくり聞き支える
子供が勇気を出していじめ被害を打ち明けてくれたら、途中で遮らずに最後まで話を聞いてあげてください。子供にとって親に話すことは大きな決断です。「よく話してくれたね」「あなたは悪くないよ」といった言葉で受け止め、子供の気持ちに寄り添いましょう。
決して子供を責めたり、「気にしすぎじゃないか?」などと言って否定したりしないでください。親に否定されると、子供は「相談しても無駄だ」と感じて心を閉ざしてしまいます。
もし子供が話しづらそうにしている場合は、無理に問い詰めず子供のペースに合わせます。おしゃべりしやすい雰囲気を作り、安心感を与えることで、ぽつぽつと本音を話し始めてくれるかもしれません。
大切なのは、親が全面的に味方であると示すことです。親が味方であると分かれば、子供は安心感を得てこれからの対応にも協力してくれるでしょう。親として「お父さん(お母さん)が必ず守るからね」と約束し、心強い味方であることを伝えてあげてください。
子供は長い間ひとりで悩み苦しんでいたかもしれません。その思いを親がしっかり受け止め、「もう一人じゃないよ。一緒に頑張ろうね」と伝えることで、子供の不安はぐっと軽くなるでしょう。
いじめの事実関係を確認し記録する
子供から話を聞いたら、いつ・どこで・誰に・どのようないじめを受けたのか、事実関係をできるだけ詳しく把握します。
日時や場所、加害児童の名前、具体的な被害内容などをノートに整理して書き留め、可能であれば写真やメール・チャットの画面保存など客観的な証拠も集めてください。例えば、子供の体にあざや怪我がある場合はスマホで写真に残し、必要に応じて医師の診断書をもらうことも検討します。
また、SNS上での誹謗中傷や悪口のメッセージがあるなら、そのスクリーンショットを保存しておきましょう。証拠として保存するとともに、念のためオリジナルのデータは削除せず保全しておくことも重要です。
これらの記録は、後で学校や第三者に状況を説明する際や、法的措置を検討する際に非常に役立ちます。子供から聞いた情報は日付順に時系列でまとめておくと、いじめの全体像が見えやすくなります。事実を客観的に整理することで、親自身も落ち着いて状況を把握でき、今後の対応方針を考える助けとなるでしょう。
集めた情報や証拠は、この後学校や専門家に相談する際の大きな武器になります。子供にも「しっかり証拠を集めたからもう大丈夫。一緒に解決しようね」と伝え、安心させてあげましょう。
【関連記事】
>LINEによるいじめの対処法とは?内容証明による解決
子供のいじめで親にできること:学校への相談と働きかけ
![]()
このトピックでは、学校と連携していじめ問題を解決へ導くために、親が取るべき行動を解説します。担任の先生への相談から学校への正式な要望、教育委員会など第三者機関の活用まで、学校側に適切な対応を促すステップです。早い段階で学校と協力し、いじめを止めることが肝心となります。
担任教師・学校への相談
いじめの事実を把握したら、できるだけ早く学校に伝えましょう。まずは担任の先生や学年主任など、日頃お子さんの様子を見ている教員に相談します。冷静かつ丁寧な姿勢で事実を伝え、学校側の見解や対応策を確認しましょう。
前段階でまとめた「いつ・どこで・誰に・何をされたか」という具体的な情報を先生に伝えることで、学校も状況を把握しやすくなります。先生とは感情的に対立するのではなく、「子供を守るために協力したい」という姿勢で臨むことが大切です。
また、当面は加害児童と席を離す、休み時間には教師が子供に目を配ってもらうなど、安全確保の措置を取ってもらうよう依頼しましょう。話し合いの際には、できれば配偶者や信頼できる親族に同席してもらうと安心です。
一人では冷静さを欠いてしまう場合もありますし、第三者がメモを取ることで後日の確認にも役立ちます。面談後は、学校側が約束した対応策や今後の連絡方法などを確認し、必要であれば日時や担当者名を記録に残しておきましょう。
学校への正式な要求書提出
担任の教師に口頭で伝えただけでは事態が改善しない場合や、いじめの深刻度が高い場合は、校長先生や学校の担当部署(生徒指導担当など)に対して書面で要望を伝える方法が有効です。いじめの詳細な状況と、子供の安全確保や加害児童への指導・再発防止策の実施を求める内容を文書にまとめ、学校宛てに提出します。
書面で残すことで、学校側も正式な対応を検討せざるを得なくなります。必要に応じて学校内にいじめ対策のための委員会(ケース会議)を設置し、教職員全体で対処に当たるよう求めることも考えられます。
この際、単に感情的な抗議をぶつけるのではなく、「いじめ防止対策推進法に基づき適切な対応を求めます」など、法律や校則に則った冷静かつ具体的な文面にすることがポイントです。
例えば要求書には、「◯年◯月◯日より◯◯中学校◯年◯組の◯◯さん(加害児童)から暴行や恐喝を受け、◯◯の怪我を負った。ついては直ちに事実関係を調査の上、当該生徒への指導と再発防止策を講じてください」など、事実と要請内容を明記します。
そして「◯年◯月◯日までに文書で回答をお願いします」と学校側に対応の期限を設けるのも良いでしょう。要求書を提出した後は、学校からどのような対応策が取られるのか、進捗を定期的に確認します。学校側もいじめ問題を放置すると責任問題になり得るため、書面による申し入れは真剣に受け止められるはずです。
【関連記事】
>子どものいじめ調査を学校に要求する正しい手順
第三者機関や教育委員会への相談
学校に働きかけても改善が見られない場合や、学校対応に不信感がある場合は、地域の教育委員会やいじめ問題の相談窓口に相談する方法があります。自治体の教育委員会は学校を指導・監督する立場にあり、重大ないじめ事案に対して調査や指導を求めることができます。
特に、子供が長期間欠席を余儀なくされている場合や深刻な心身の被害を受けている場合は、「重大事態」として教育委員会が動くケースもあります(いじめ防止対策推進法により、生徒が相当の期間学校を欠席するなど重大事態と認められる場合、学校は教育委員会に報告し調査が義務付けられています)。
教育委員会への相談は電話や書面で行うことができ、必要に応じて直接担当者と面談することも可能です。第三者の力を借りることで、学校も対応を改めるきっかけになるでしょう。また、自治体には教育相談センターや子どもの人権110番といった専門の相談窓口もあります。文部科学省が設置している24時間対応の「いじめ相談ダイヤル」を利用することもできます。
さらに、法務局の「子どもの人権110番」や、民間NPO法人が運営するいじめ相談ホットラインなど、行政以外の相談窓口も存在します。困ったときは遠慮せず、利用できる制度や団体を頼りましょう。
このような公的機関のサポートを積極的に活用し、学校だけでなく社会全体で子供を守る体制を整えましょう。
子供のいじめで親ができること:法的措置と内容証明郵便の活用
![]()
このトピックでは、学校への働きかけだけではいじめが収まらない場合に、法的な手段や専門家の力を借りる方法について説明します。内容証明郵便による正式な通知で加害者側や学校に圧力をかける方法や、行政書士・弁護士といった専門家への相談について解説します。
必要に応じて法的措置も視野に入れることで、いじめ問題の早期解決を図ります。
内容証明郵便で正式に通知を行う
学校への要望や話し合いを重ねてもいじめが続く場合や、初期段階でも早急に強い対応が必要だと判断した場合には、内容証明郵便を活用して加害児童の親や学校に対し正式に通知を送る方法があります。
内容証明郵便とは、郵便局が「いつ・誰から誰宛てに・どんな内容の手紙を送ったか」を証明してくれる郵便サービスです。これを利用して、いじめの事実と要求事項(いじめの即時停止や再発防止策の実施など)を公式な書面として相手に突き付けることで、公的な記録を残しつつ相手に心理的なプレッシャーを与える効果が期待できます。
公式な書面を受け取った学校や加害者側は、いじめ問題が法的な問題に発展し得る重大な事態であることを認識し、もはや無視できなくなるでしょう。なお、加害児童の親と直接顔を合わせて話し合うことはお互い感情的になりトラブルに発展しがちですが、書面での通知であればそうした心配も少なく、冷静かつ毅然とした姿勢を示すことができます。
内容証明郵便(窓口持ち込み型)は同じ内容の文書を3通作成し、一通は郵便局に保管されます。郵便料金の他に内容証明の手数料が数百円ほどかかりますが、公的証拠を残す手段として有効です。
内容証明で通知した事実自体が後々の証拠となり、例えば「何月何日から何月何日までどのようないじめ被害を受けたか」といった時系列や被害の深刻さを明確に示す資料にもなります。送付先は、いじめを行った加害生徒の保護者や学校の校長先生など、その問題に対して責任ある立場の相手を選ぶことが重要です。
適切な相手に送ることで、校内で情報が共有され、迅速かつ具体的な対応が取られやすくなるでしょう。さらに、内容証明郵便で通知を行った後に相手がなおも改善しない場合は、「学校の安全配慮義務」や「保護者の監督義務」が十分に果たされていないことの証明にもなり得ます。つまり、内容証明の送付は将来的に法的責任を問う際の強力な武器にもなります。
【関連記事】
>いじめの記録は内容証明郵便が効果的?行政書士がサポート
行政書士に依頼するメリット
内容証明郵便による通知書はご自身で作成・送付することも可能ですが、法的な観点からは専門家である行政書士に依頼するのがおすすめです。行政書士は法律に基づいた文書作成のプロフェッショナルであり、専門性があればいじめ問題に関する通知書作成にも精通しています。行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
法律に沿った適切な文面
行政書士は関連法規や判例を踏まえた表現で文書を作成できます。これにより、要求に正当性を持たせつつ、相手に法的責任を明確に認識させる内容の通知書が作れます。依頼者である親御さんの話を丁寧にヒアリングした上で、感情的な表現は避け、法律用語も交えながら適切な言葉に言い換えてくれるため安心です。
正式な文書としての信頼性
専門家が関与した通知書であることから、受け取った相手に「正式な手続きが取られている」という強い印象を与えられます。親が個人で出す手紙よりも重みがあり、無視されにくくなる効果があります。実際に行政書士等の名前が文書に記載されているだけで、先方の態度が真剣になるケースもあります。
リスク回避と安心感
行政書士が文案をチェックすることで、感情に任せた表現による名誉毀損や脅迫・恐喝と受け取られかねない表現を避け、安全な内容に仕上げられます。法律のプロが作成するので「言い過ぎて法に触れないか」といった心配も軽減され、親御さんも安心して相手に意思表示ができます。
そのほか、行政書士に依頼すれば内容証明郵便の作成から郵送手続きまで一括して代行してもらえるため、初めての方でも手間取る心配がありません。
行政書士事務所によっては全国対応でメールや電話相談を受け付けているところも多く、遠方にお住まいの場合でも依頼しやすいでしょう。いじめ問題に対する豊富な経験を持つ行政書士であれば、過去の事例も踏まえた有効なアドバイスをもらえるでしょう。
安価に済む場合が多いため、経済的な負担を抑えたい方にも利用しやすいと言えます(具体的な費用は依頼内容や事務所によって異なりますので、事前に見積もりを確認しましょう)。
弁護士や警察など他の専門家への相談
内容証明郵便を送付してもいじめが改善されない場合や、子供が大怪我を負わされた・金品を強要された等の明らかな犯罪行為が含まれる場合には、弁護士や警察といった他の専門家に相談することも視野に入れましょう。
弁護士に相談すれば、加害者や学校に対する損害賠償請求や法的措置(仮処分申立てや訴訟など)の検討、相手方との交渉を代理人として依頼できます。例えば、いじめによって子供が不登校や精神的疾患に陥った場合、加害者側の保護者に対し民法上の監督責任(民法第714条)に基づく損害賠償を請求することも可能です。
また、学校側に対しても適切な対応を怠った安全配慮義務違反として責任を問えるケースがあります。内容証明を送ったにもかかわらず相手から誠意ある反応がない場合、実際に法的措置に踏み切る姿勢を見せることで状況が動く場合もあります。
もちろん、事前に内容証明郵便で通知を行っていた事実は「警告したのに改善されなかった」証拠にもなり、裁判の際には有利に働く可能性があります。なお、暴行・恐喝など刑事事件に該当するいじめであれば警察に被害届を出すことも検討してください。
ただし、警察沙汰や裁判となると子供への心理的負担も大きくなります。専門家に委ねるタイミングはケースバイケースですが、まずは内容証明郵便や学校・教育委員会での対応で解決を図り、それでも収まらない深刻な場合の最終手段として弁護士や警察を頼るのが良いでしょう。いずれにしても、保護者だけで抱え込まず必要に応じて外部の力を借りることが大切です。
子供のいじめで親ができること:子供の心のケアと再発防止
![]()
このトピックでは、いじめ問題への対処と並行して重要な、被害に遭ったお子さんの心のケアや今後の再発防止策について説明します。いじめを受けた子供の心の傷を癒し、自信を取り戻させるとともに、再び同じような被害に遭わないよう家庭でできるサポートをまとめます。
解決策を講じる間も、子供の心身のケアを怠らないようにしましょう。
子供の心のケアと安心できる環境作り
いじめから子供を守る上で、親ができる最も大切なことの一つは子供の心のケアです。子供はいじめによって深く傷つき、自分に自信をなくしているかもしれません。毎日しっかりと声をかけ、愛情を伝えてください。「あなたは大切な存在だよ」「もう安心していいからね」といった言葉やスキンシップで安心感を与えましょう。
子供によっては一見平気なふりをしていることもありますが、内心は強いストレスを抱えているものです。できれば毎日決まった時間に子供との対話の時間を持ち、「今日は学校で何か嫌なことはなかった?」と優しく尋ねる習慣を作るのも良いでしょう。
また、必要に応じて学校のスクールカウンセラーや児童心理の専門家に相談し、プロのカウンセリングを受けさせることも検討してください。第三者に話を聞いてもらうことで、子供が抱える不安やトラウマの緩和につながります。
家庭では子供がリラックスできる時間と空間を用意し、安心して過ごせる環境作りを心がけましょう。子供が家では心休まる状態を保つことが、学校で受けたストレスを癒す第一歩となります。また、子供が信頼できる友達や親戚がいれば、その人たちにも協力をお願いし、子供が一人で悩まないような支えの輪を作ることも大切です。
自己肯定感を高めるサポート
いじめによって傷ついた子供の自己肯定感を回復させることも重要です。子供の良いところや頑張っている点を日々認め、「よく頑張っているね」「あなたにはこんないいところがあるね」と積極的に伝えてください。
いじめられた事実は決して子供の価値を損なうものではないと理解させ、自信を取り戻せるよう支えます。親として悔しい気持ちから「やり返して来い」と発破をかけたくなるかもしれませんが、それは子供を追い詰めてしまう可能性があります。
復讐を促すのではなく、「あなたは何も悪くない」ということを繰り返し伝えましょう。子供が興味や関心を持つことに打ち込めるような機会を与えるのも効果的です。部活動や習い事、趣味などに集中することで成功体験を積み、自己肯定感の回復につなげられるでしょう。
また、必要であれば環境を変えることも選択肢に入れてください。いじめた側との物理的な距離を置くために、クラス替えを学校に相談したり、場合によっては転校を検討する家庭もあります。転校は最後の手段かもしれませんが、新しい環境で気持ちをリセットし、のびのび過ごせるようになるケースもあります。子供の気持ちを第一に考え、安全に安心して学べる環境を探ることも時には大切です。
継続的な見守りとオープンな対話
いじめ問題が一応解決したように見えても、再発防止のために親が引き続き注意を払うことが必要です。日々の会話の中で学校での様子をさりげなく聞いたり、子供の態度や表情の変化に気を配ったりしましょう。
子供が再び何か悩みを抱えてもすぐ相談できるよう、「何かあったらいつでも話してね」と伝え、オープンな雰囲気を保つことが大切です。また、学校とも定期的に連絡を取り合い、いじめ再発の兆候がないか情報共有しておくと安心です。担任の先生だけでなく、学年主任やスクールカウンセラーとも連携し、学校全体で子供を見守ってもらえる体制を築きましょう。
さらに、保護者自身もPTAや学校行事に参加して学校の雰囲気を把握し、人間関係に目を配っておくと変化に気付きやすくなります。兄弟姉妹がいる場合は、兄弟間で悩みを共有したり、学校でさりげなく気にかけてもらったりすると心強いでしょう。
また、他の保護者と情報交換をしたり、PTAの場でいじめ問題について提起し、学校全体の意識を高めることも再発防止に有効です。家庭と学校が協力して見守ることで、万一小さないざこざが起きても早期に対処し、大きないじめに発展するのを防ぎやすくなります。
子供との信頼関係を維持しつつ周囲の大人とも連携し、長期的に安心して学校生活が送れるようサポートしていきましょう。
子供のいじめ被害において親ができることーまとめ
子供がいじめ被害に遭ったとき、親ができることは多岐にわたります。家庭での支えと学校への働きかけ、そして必要に応じた法的手段の活用まで、段階的に対応策を講じることで事態の好転が期待できます。
親としては感情的になりすぎず冷静に対処しつつ、子供の心に寄り添って守ってあげることが何よりも重要です。いじめ問題は放置すると深刻化する傾向がありますが、適切な行動を取れば必ず解決への道は開けます。
もし加害者側への通知書や学校への書面作成に不安がある場合は、ぜひ当行政書士など書類作成の専門家に相談してください。法律のプロである行政書士は、親御さんの気持ちに寄り添いながら適切な文書作成と手続きをサポートいたします。
専門家の力も借りつつ、一人で抱え込まないことが大切です。いじめに立ち向かうのは決して簡単ではありませんが、親が諦めず行動すればきっと状況は変えられます。周囲と協力しながら、お子さんにとって安全で安心できる環境を取り戻してあげましょう。いじめに苦しむお子さんが再び笑顔を取り戻せるように、親子で力を合わせて決してあきらめずに問題に立ち向かうことが大切です。
いじめに関する内容証明郵便の作成はお任せください
![]()
子供のいじめ問題に直面したとき、保護者の方だけで学校や加害児童の保護者と向き合うのは大きな負担になります。感情的になりすぎず、しかし毅然とした姿勢を示すためには、第三者である専門家が作成した「正式な書面」が大きな力を発揮します。
当事務所では、いじめに関する内容証明郵便・要望書・通知書の作成を多数取り扱っています。とくに次のようなケースでご相談をいただくことが多くあります。
- 学校(担任・校長)に対して、いじめの事実調査や安全確保、具体的な再発防止策の実施を正式に求めたい場合
- 加害児童の保護者に対し、いじめの即時中止や謝罪、今後一切の接触・言動の自粛を文書で求めたい場合
- 学校側の対応が不十分なため、いじめ防止対策推進法や学校の安全配慮義務を踏まえた要望書・通知書を送りたい場合
- 不登校や転校を余儀なくされたことによる精神的苦痛や経済的負担について、後日の損害賠償請求も見据えて記録と証拠を残しておきたい場合
- 将来、教育委員会や弁護士・裁判所等に話が進んだときに備えて、「いつ・どのような要請を行ったか」を客観的な証拠として残しておきたい場合
これらの文書は、強すぎる表現は名誉毀損や脅迫・恐喝と評価されるリスクもある一方で、弱すぎると何も伝わらず「単なる苦情」で終わってしまう難しい分野です。
当事務所では、保護者の方のお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、法律的な観点から表現を調整し、安全性と実効性のバランスが取れた内容証明郵便を作成いたします。まずは現在の状況をお聞かせください。保護者の方とお子さんに寄り添いながら、最適な文書や対応方法をご提案いたします。
手続の流れ
1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。
| ⑴ お電話によるご相談は→0743-83-2162(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |
2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。
3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。
4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成しご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)
5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。
6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。
【郵送書類】
- 内容証明郵便の謄本 計1通
- 配達証明書 計1通
- 領収書 計1通
- その他書類(名刺、アンケート等)
以上が大まかな手続の流れでございます。
ご依頼いただくメリット
下記には、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。
メリット1 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。
メリット2 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。
行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができます。
メリット3 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)
しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。
ご依頼料金
下記の料金には、当事務所の記名費用を含んでおります。 (一部のサービスでは記名できない場合がございます。) 内容証明の郵送費等は別途かかります。
| 業務内容 | 案件(受取方) | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 内容証明の作成と差出 | 定型外文面(個人・法人) | 33,000円~ | 1,000文字から4,000文字(最大)程度の内容文書を作成します。 |
| 内容証明トータルサポート | サービスによってご利用いただけます。 | 44,000円~ | 〃 |
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。
そのため、実施するサービスには自信をもっております。
![]()
内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。なお、金額によってページ数は異なります。
![]()
【参考記事】
日本郵便株式会社 内容証明