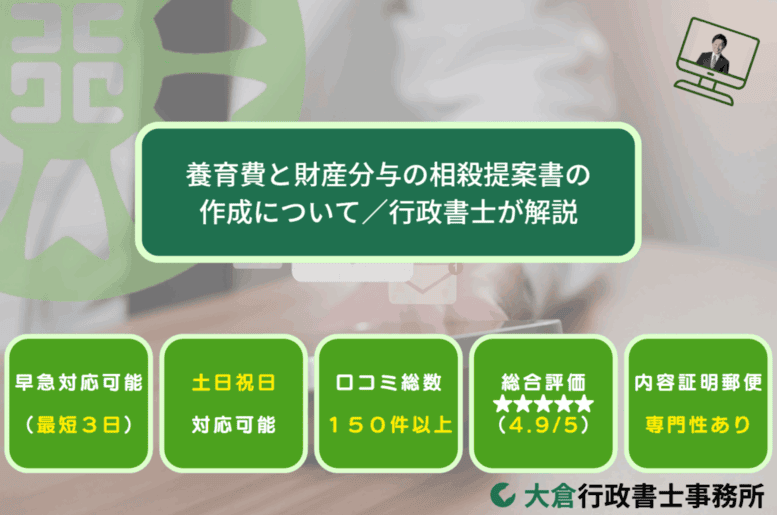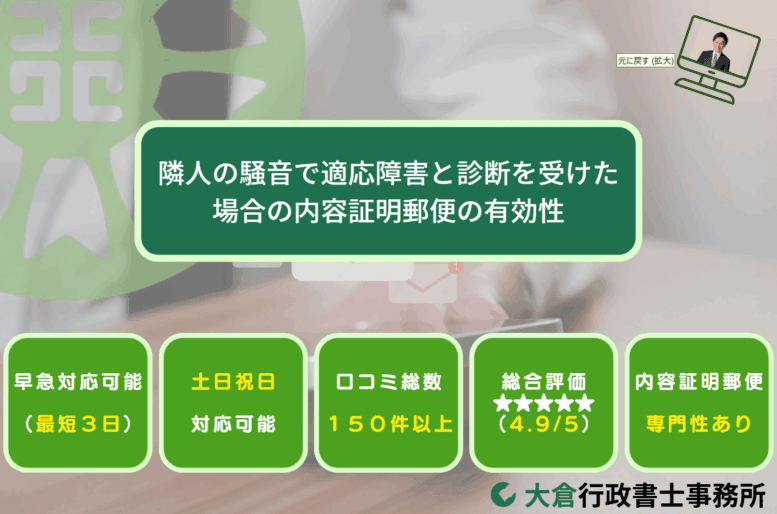離婚に際して取り決められる「養育費」と「財産分与」は、どちらも大切なお金の問題です。しかし、もし相手が養育費を支払っていないまま、自分が相手に財産分与金を支払わなければならない状況になったらどうでしょうか。
このような場合、「未払いの養育費と支払うべき財産分与を相殺して一括清算できないか?」と考える方も少なくありません。実際、養育費の不払いが続いているために、財産分与金の支払いを留保し、双方の債務を相殺する提案を行うケースもあります。
本記事では、行政書士が養育費と財産分与の相殺提案書の作成方法について解説します。養育費と財産分与の基本、相殺の可否やメリット、提案書作成のポイント、そして専門家である行政書士に依頼するメリットまで、具体例を交えながら詳しく説明します。相手との金銭問題を円満に解決したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
養育費と財産分与の基礎知識と相殺を検討する背景
![]()
このトピックでは、離婚時に取り決められる養育費と財産分与の基本を整理し、養育費が未払いとなっている中で財産分与金の支払いが生じる場合に、両者の相殺を検討する背景について解説します。養育費や財産分与がどのような性質のお金かを理解し、なぜ相殺という発想が出てくるのかを把握しておきましょう。
養育費の未払いがもたらす問題
養育費は、子どもの健やかな成長のために離婚後も支払い続ける必要がある大切な費用です。一般的に、非監護親(子どもと一緒に暮らしていない親)が監護親に対し、子が社会人として自立するまでの生活費や教育費などを継続的に支払うものとされています。
養育費の支払い終期(いつまで支払うか)は夫婦間の協議や調停で自由に定められ、多くの場合は子どもが20歳または18歳に達するまで、あるいは大学卒業時までなどと取り決められます。
しかし、経済的事情や対立から養育費の不払いが起きてしまうケースも少なくありません。養育費の未払いが続くと、監護親(受け取る側)は子どもの生活費を一人で賄う負担が生じ、子どもの生活安定にも影響が及びます。
本来、調停調書や公正証書で取り決めた養育費は強制執行も可能な法的義務ですが、相手に支払い能力がない場合や手続きの手間などから、すぐに回収できないこともあります。養育費が支払われないまま滞る状況は、受け取る側にとって大きな不安と不満を生じさせるでしょう。
離婚時の財産分与と支払い義務
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を離婚時に公平に分配する制度です。典型的には、不動産や預貯金などの共有財産を夫婦それぞれの貢献度に応じて分け合います。離婚協議や調停において、財産分与の方法や金額が定められ、一方が他方に対して現金で支払うケースも多くあります。
財産分与金の支払いは離婚後比較的早期に一括で行われるのが通常ですが、不動産の売却など時間を要する手続きが絡む場合は、協議書や調停調書(家庭裁判所の調停での合意記録)などで具体的な支払期限が定められ、支払う側はその内容に基づき支払いを履行する必要があります。
【関連記事】
>離婚協議書による財産分与の書き方
>離婚協議書の養育費の書き方は?
養育費と財産分与の相殺を検討する状況とは
相手から養育費が支払われていない状態で、自分が相手に対して財産分与金を支払う義務を抱えている場合、双方の債務を相殺してしまいたいと考えるのは人情と言えるでしょう。
具体的には、例えば元夫が長期間にわたり養育費を滞納している一方で、元妻が離婚時の合意に基づき元夫に財産分与として高額の金銭を支払わなければならないようなケースです。
養育費を受け取っていないのに自分だけ相手に大金を支払うのは不公平に感じられるため、「未払い養育費と財産分与金を相殺(差し引き)して、清算した残額のみ支払う」という解決策が頭に浮かぶわけです。
このような発想は、当事者間で金銭のやりとりをシンプルに済ませ、紛争を早期に終わらせたいという動機から生まれます。特に、離婚後に繰り返しトラブルとなっている場合、一度きりの決着でお互いの債権債務関係を清算し、今後の争いを断ち切りたいと考えるでしょう。養育費と財産分与の相殺提案は、そうした状況下で浮上する解決策の一つなのです。
養育費と財産分与の相殺は可能か?法律上の原則と現実的な解決策
![]()
このトピックでは、養育費と財産分与を相殺することの法律上の扱いについて解説します。
原則として養育費は相殺が認められない理由と、その一方で当事者間の合意によって現実的な解決を図る方法について見ていきましょう。
相殺提案を行う前提として、法律上の制約と合意形成の重要性を理解することが大切です。
養育費に対する相殺禁止の原則
結論から言えば、法律上は養育費と財産分与を一方的に相殺することは認められていません。これは養育費が持つ特別な性質によるものです。養育費は子どもの生活を維持するためのものであり、子どもの健全な成長を守るために法的にも強く保護されています。
さらに、養育費は「子どもの権利」であるため、親の一存で放棄したり減額したりできない性質があります。仮に夫婦間で「養育費を受け取らない代わりに財産分与を多めにもらう」といった合意をしても、子ども自身はその合意の当事者ではありません。
このように、養育費と財産分与はそもそも性質が異なるため、本来は当事者の都合で相殺できる類のものではないことをまず押さえておきましょう。
当事者間の合意による解決の必要性
法律上は養育費と財産分与の相殺が認められないとはいえ、現実問題として冒頭で述べたような事情(養育費の長期不払いと高額な財産分与金の支払い義務)があれば、当事者としては何とかしたいと思うはずです。
その解決策として考えられるのが、当事者間の合意による債権債務の清算です。つまり、法律上の形式的な相殺ではなく、「養育費の支払終期を見直して支払総額を減らし、その金額を財産分与金と相殺する」という内容の新たな合意を夫婦間で結ぶ方法です。
ポイントは、あくまで双方が納得の上で合意することにあります。一方的に「養育費分を差し引いて財産分与金は減額する」と主張しても、法的には相手にその通りの履行を強制できません。
相手方にもメリットがある提案内容を示し、話し合いによって同意を取り付ける必要があります。そのための手段として作成するのが「相殺提案書」というわけです。
双方が合意すれば、当事者間の契約として新たな条件で養育費と財産分与の問題を解決することが可能になります。合意内容を書面に残し署名押印しておけば、後々の紛争予防にも役立つでしょう。
相殺提案のメリットと注意点
養育費と財産分与の相殺による解決には、いくつかのメリットがあります。まず、金銭問題を一度で清算できるため、長期化しがちな養育費の支払いトラブルを早期に終わらせることができます。
提案が受け入れられ合意に至れば、以後は養育費の支払いを巡って争う必要がなくなり、精神的な負担も軽減されるでしょう。また、相手方にとっても将来的な支払い負担が減るなどの利点がある場合、合意に応じてもらいやすくなります。
実際に相殺提案を成功させたケースでは、相手方(養育費支払義務者)が総額数百万円規模の負担軽減となる条件を提示することで、前向きな同意を得ることができました。双方にとってメリットがある形で解決を図れる点は相殺提案の大きな魅力です。
一方で、注意すべき点もあります。養育費の減額や権利放棄につながる合意は、本来子どもの利益に反する恐れがあるため慎重に検討する必要があります。子の将来を考慮し、無理のない範囲で減額幅を決めることが望ましいでしょう。
さらに、合意に基づく解決とはいえ法的に完全に無効とならない保証はないことも認識しておきましょう。極端に養育費をゼロにするといった取り決めは後から無効主張されるリスクがあります。ですから、合意内容はあくまで当事者がお互い納得できる範囲で、公平性に配慮したものにすることが大切です。
最終的には書面を交わし、双方が自発的にその約束を守ることによって現実的な効力が生まれるものと言えます。
【関連記事】
>協議離婚の要求を内容証明郵便で行うには?
相殺提案書の作成方法と成功させるポイント(具体例あり)
![]()
このトピックでは、実際に養育費と財産分与の相殺提案書を作成する際のポイントを詳しく解説します。
どのような内容を盛り込めばよいのか、文章の構成や注意点は何か、そして実際に相殺による解決を実現した具体例を紹介します。
適切な提案書を作成することで、相手にとっても魅力的な解決策であることを示し、合意を引き出す可能性が高まります。
相殺提案書に盛り込むべき内容
相殺提案書を作成する際には、以下のような内容を盛り込むとよいでしょう。
現状の確認と問題提起
まず、現在の状況を整理しましょう。離婚時の調停調書や契約で取り決めた養育費額・支払終期、財産分与金の額・支払期限を明示し、それぞれの債務がどうなっているかを説明しましょう。
特に養育費が未払いになっている場合は、何月から支払いが滞り、いくら未払いになっているのか具体的な金額を示しましょう。これにより、問題の所在(養育費不払いによる不公平感)が明確になります。
支払い留保の経緯と心情
次に、相手の養育費不払いにより自分がどのような心情になっているか、現状で財産分与金を支払うことに納得がいかない旨を伝えましょう。ただし感情的な非難は避け、あくまで事実に基づき冷静に述べることが重要です。
「養育費が約束通り支払われていない状況では、約定どおり財産分与金を支払うことに複雑な心情を抱いています」といった表現で、自分の立場と考えを丁寧に説明しましょう。
また、場合によっては既に財産分与金の支払期限が過ぎていること、支払いを保留している理由が相手側の不履行に起因することも述べておきましょう。
解決策(相殺提案)の提示
続いて、本題である解決策を提案しましょう。「早期解決のため、養育費債権と財産分与債務の相殺による解決を提案いたします」等の文言で切り出し、具体的な提案内容を示しましょう。
具体例としては「養育費の支払終期を○○から○○に繰り上げ、その結果生じる養育費総額を貴殿に支払うべき財産分与金と相殺したい」といった形になります。
ポイントは、単に相殺すると言うだけでなく、養育費の条件変更によって相手方にどれだけメリットがあるかを数字で示すことです。
提案内容の詳細と試算
提案の中身を数字を用いて明示します。たとえば「当初の取り決めでは養育費支払総額は○○円(子ども一人当たり○○円×○○か月)でしたが、提案後の支払終期変更により総額○○円(○○円×○○か月)に減額されます。
その結果、貴殿の負担は合計で○○円(○○万円)軽減されます」というように、相手方の負担減少額を具体的に計算して示します。
| (例)養育費の終期を「22歳の年の3月」から「18歳の年の3月」に繰り上げることで、子ども2人分の支払総額を2,000万円から1,500万円に減額し、相手方は合計500万円も支払い負担が減る提案等 |
このように数値を挙げることで、提案の有利さがひと目で伝わるでしょう。
相殺後の清算金額
次に、相殺を行った場合に最終的に支払うべき清算額を提示しましょう。養育費総額を財産分与金から差し引いた残額を算出し、「上記相殺後の支払残額として金○○円をお支払いします」と明記しましょう。
具体的には「財産分与額○○円と養育費債務○○円を相殺した結果、清算額(支払額)は○○円となります」と記載しましょう。相殺によってお互いの金銭請求をすべて精算し、この清算額の支払いで最終決着としたい意向を伝えましょう。
合意書への署名依頼と期限
提案内容に同意してもらえる場合の手続きを案内しましょう。通常は、相殺の合意内容を正式な契約書(合意書)に落とし込み、署名押印してもらう必要があります。
そのため、「本提案にご同意いただける場合は、別紙の合意書に署名押印の上、○月○日(期限)までにご返送ください」といった形で具体的な対応をお願いしましょう。
期限を設けることで、先延ばしを防ぎ早期決着を促す効果があります。また、合意書の返送先や返送方法(返信用封筒やレターパックの同封など)についても記載しておくと親切です。
支払い実行の約束
相手から合意書が届いた後の自分の履行についても明記しましょう。例えば「ご署名いただいた合意書を受領次第、同書記載の期日までに相殺後の残額○○円を指定口座にお振込みいたします」と約束しましょう。
これにより、相手は合意書さえ返送すれば速やかにお金を受け取れると分かり、提案を受け入れやすくなります。
締めくくりと前向きなお願い
最後に、提案書全体の締めくくりとして丁寧に協力をお願いする一文を添えましょう。長引く紛争を終わらせたい気持ちや、本提案が相手にとっても損のない有利な内容であることを改めて強調し、「ぜひ前向きにご検討ください」と結ぶと良いでしょう。
必要に応じて、「本合意により養育費・財産分与に関する相互の債権債務が最終的に清算されたことを確認する。また、今後お互いに金銭請求を行わない」ことを約束する文言なども別紙合意書に盛り込むため、その点も簡潔に触れておくと親切です。
提案書作成時の注意点
相殺提案書を作成する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。まず第一に、冷静で公正な書きぶりを心がけることです。相手の養育費不払いに不満があっても、感情的な非難や攻撃的な表現は避けましょう。
あくまで事実と数字に基づいて淡々と状況を説明し、建設的な解決策を提示する姿勢が大切です。丁寧で礼節をわきまえた文面にすることで、相手にも誠意が伝わりやすくなります。
次に、相手にとってのメリットを明確に打ち出すことが成功の鍵です。相手が合意したくなる提案でなければ、相殺による解決は実現しません。提案内容が相手にどれだけ有利か(将来的な支払い負担が大幅に減る等)を具体的な数字をもって示し、「この方法ならあなたにも大きな利点があります」と分からせる工夫をしましょう。
上記で述べたように、数百万円単位の負担軽減となる試算を提示できれば、相手の心も動きやすくなります。
また、提案書や合意書の形式面にも注意が必要です。正式な文書として体裁を整え、日付・当事者氏名(双方)・タイトル・段落構成などをきちんと整えましょう。行政書士など専門家の力を借りれば、公正で読みやすい文書に仕上がります。
相殺提案を成功させた具体例の紹介
※本事例は実際のケースに基づいていますが、金額等はプライバシー保護の観点から一部変更しています。なお、当該相殺提案は依頼者ご本人の意思に基づき作成されたものであり、当事務所が内容の提案・交渉・助言を行ったものではありません。
ケース概要
離婚調停により、元夫は長男・次男の養育費として「子が22歳に達する年の3月まで、月額合計12万円(各子6万円)」を支払うことが定められていました。一方、元妻は財産分与として、自宅マンションの売却代金から2500万円を元夫に支払う内容で合意していました。
しかし離婚後、元夫は令和5年12月以降養育費の支払いを停止し、令和7年11月時点で未払い養育費は288万円(12万円×24ヶ月)に達していました。元妻も養育費不払いのままでは納得できず、財産分与金の支払いを保留したまま、双方の金銭債権が宙に浮いた状態となっていました。
提案内容(依頼者本人の判断による)
元妻は、問題解決のために養育費の支払終期を「22歳に達する年の3月」から「18歳に達する年の3月」へ繰り上げる案を元夫に対して提案しました。
- 長男:160ヶ月→112ヶ月(減額額:288万円)
- 次男:184ヶ月→136ヶ月(減額額:288万円)
合計で将来的な養育費支払額が576万円減額となる試算です。この養育費減額を前提に、元妻は「財産分与金2500万円から養育費分576万円を相殺し、残りの1924万円を支払う」との内容を記した合意書案を作成し、署名返送を依頼しました。
結果とポイント
養育費の負担が軽減され、さらに1924万円を一括で受け取れるという条件が現実的であったため、元夫は提案を受け入れ、合意書に署名。元妻は予定どおり残額を支払ったことで、双方の金銭債権・債務は清算されました。
この事例は、依頼者自身による柔軟な条件調整により、法的な対立を回避し円満に解決できた好例といえます。
行政書士に依頼するメリットとサポート内容
![]()
このトピックでは、養育費と財産分与の相殺に関する合意書や提案書の文案作成にあたり、行政書士に相談・依頼するメリットについて解説します。行政書士は官公署に提出する書類や、契約書・合意書などの権利義務に関する文書の作成業務を行う国家資格者です。
専門家のサポートを受けることで、形式的・法律的に整った書類の作成が可能となり、円滑な問題解決の一助となります。また、全国対応可能な行政書士事務所であれば、遠方からの相談・依頼にも対応してもらえるため、安心して支援を受けることができます。
法律に基づいた文書作成支援が可能
行政書士に依頼する大きなメリットの一つは、法令や実務に照らした文書を形式的に整えて作成できることです。養育費や財産分与に関する合意内容は、将来のトラブル防止の観点からも、書面化しておくことが重要です。
行政書士は、離婚協議書や合意書などの文案作成に関する相談に応じることができ、文書として必要な構成や表現を整える役割を担います。
たとえば、相殺の合意書において「本件離婚に伴う養育費および財産分与に関する一切の債権債務が最終的に清算されたことを確認する」といった清算条項のように、合意内容を文書上に明確に反映させることが可能です。
なお、行政書士はあくまで文書作成に関する業務を担うものであり、相手方との交渉や代理行為は行いません。相手との交渉や法的紛争の処理を要する場合には、弁護士に引き継ぐ必要があります。
法令に照らした文案設計のサポート
行政書士は、書類作成の専門家として、依頼者からの聞き取りを通じて、養育費や財産分与に関する文案について、関係法令や過去の書式実例を参考にしながら、適切な記載内容を助言・整理することが可能です。
たとえば、養育費の金額や財産分与の方法など、依頼者自身が検討している内容を文書に落とし込む際に、法的観点から支障のない表現となるよう配慮した構成や記載例を提示することができます。
また、すでに作成済みの調停調書や公正証書との記載内容の整合性についても、文案上の調整が必要な場合には、その点を確認しながら文書作成の支援を行います。
なお、行政書士は法的紛争に関する交渉や代理行為には関与できませんが、書類の文案整理において、誤解を招かないよう配慮された記載とすることにより、将来的なトラブルの予防にもつながる支援が可能です。
合意後の契約書作成までの一貫支援(※代理交渉は除く)
相殺に関する提案に相手が応じた場合、最終的には履行に向けた正式な合意書(契約書)を作成する必要があります。行政書士に依頼すれば、合意書の文案作成も含めて一貫した書類作成支援を受けることができます。
養育費と財産分与の相殺提案についてーまとめ
養育費の不払いと財産分与の支払い義務が絡む複雑な状況でも、工夫次第で双方納得の解決策を見出すことができます。その一つが養育費と財産分与の相殺提案であり、適切な提案書と合意書を用意することで現実に問題を解決した例もあります。
ただし、子どもの権利に関わる養育費の取扱いには慎重さが求められるため、公平で無理のない条件設定が重要です。専門家である行政書士の力を借りれば、法的に整合性の取れた書類作成が得られ、安心して問題解決に臨むことができるでしょう。
養育費と財産分与の提案書作成はお任せください
![]()
当事務所では全国対応で離婚に関する書類作成サポートを行っておりますので、養育費や財産分与の問題でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
あなたの円満解決に向けて、経験豊富な行政書士がしっかりとお手伝いいたします。
手続の流れ
1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。
| ⑴ お電話によるご相談は→0743-83-2162(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |
2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。
3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。
4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成しご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)
5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。
6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。
【郵送書類】
- 内容証明郵便の謄本 計1通
- 配達証明書 計1通
- 領収書 計1通
- その他書類(名刺、アンケート等)
以上が大まかな手続の流れでございます。
ご依頼いただくメリット
下記には、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。
メリット1 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。
メリット2 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。
行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができます。
メリット3 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)
しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。
ご依頼料金
下記の料金には、当事務所の記名費用を含んでおります。 (一部のサービスでは記名できない場合がございます。) 内容証明の郵送費等は別途かかります。
| 業務内容 | 案件(受取方) | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 内容証明の作成と差出 | 定型外文面(個人・法人) | 33,000円~ | 1,000文字から4,000文字(最大)程度の内容文書を作成します。 |
| 内容証明トータルサポート | サービスによってご利用いただけます。 | 44,000円~ | 〃 |
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。
そのため、実施するサービスには自信をもっております。
![]()
内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。なお、金額によってページ数は異なります。
![]()
【参考記事】
日本郵便株式会社 内容証明