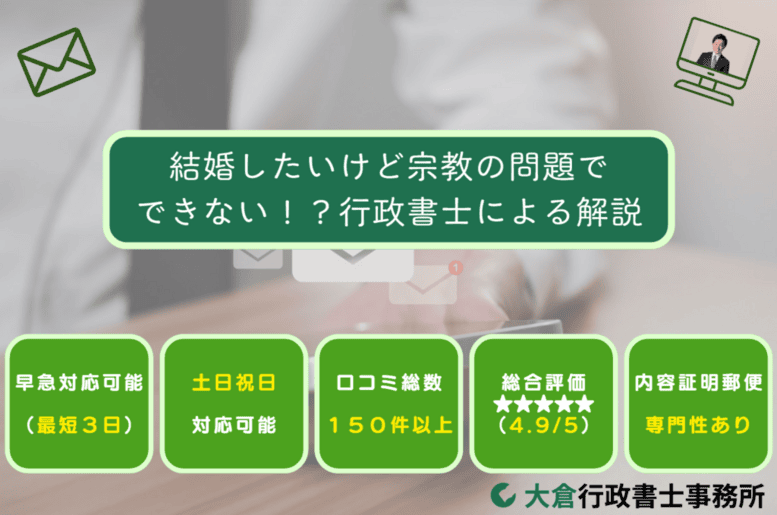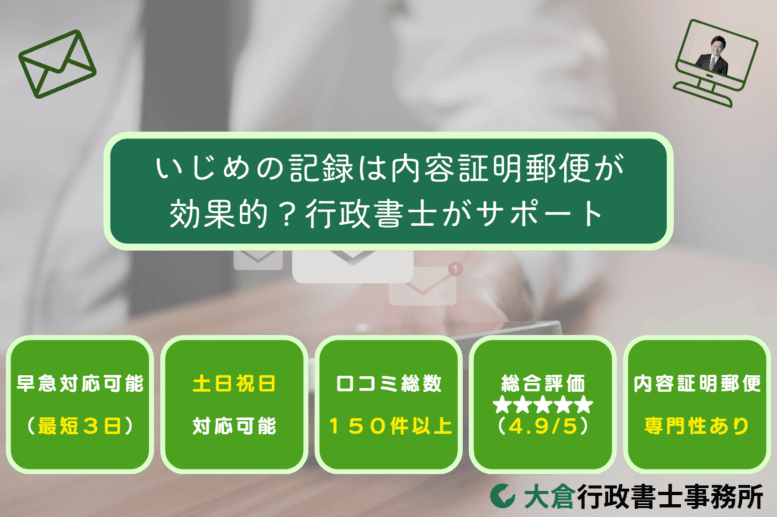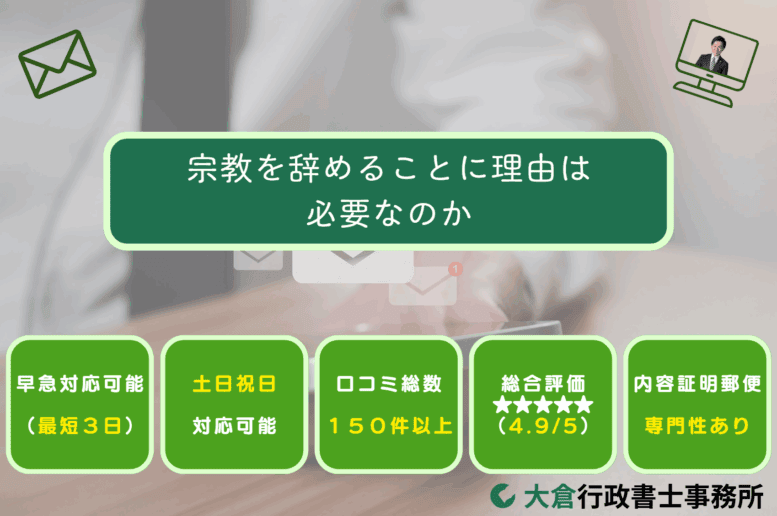「結婚したいけど宗教問題でできない」とお悩みの方は意外と多いのではないでしょうか。結婚は人生における大きな節目であり、本来は愛情や信頼を土台として築かれるべきものです。しかし、現実には「宗教」が壁となり、結婚に踏み切れない、または家族から強く反対されてしまうというケースが少なくありません。特に、片方が熱心な宗教団体に所属していたり、過去に入会させられていた経験がある場合、婚約者やその家族が不信感や不安を抱くこともあります。
宗教の問題は、当事者同士の関係だけでなく、家族・親族間にも深く影響を与えるため、感情的な対立に発展することもあるのです。
本記事では、行政書士の立場から、宗教が結婚の障害となっている方に向けて、実際に相談を受ける中で得た経験を踏まえつつ、具体的な解決策や対応法を解説いたします。
結婚したいけど宗教の問題でできないことはあるの?
![]()
この章では、信仰の違いや宗教に関する価値観の対立が、どのようにして結婚の障害になり得るのかを詳しく解説していきます。宗教の問題は、当人同士の理解だけで解決するとは限らず、家族や親族、周囲の信者の関わりによってより複雑になることがあります。
そのため、感情的な問題にとどまらず、生活上の実務的な問題や信仰継続の有無にまで関わってくるケースも少なくありません。
結論:宗教の問題で結婚できないことは実際にある
宗教的背景の違いは、結婚生活において深刻な価値観のズレを生み出すことがあります。特に以下のような場面では、その問題が表面化しやすく、結果として婚約破棄に至ることもあります。
宗教上の教義や信条の違いによる対立
代表的なのは、異なる宗教を信仰している者同士が結婚を望んだ場合です。一方の宗教が他の宗教を否定する教義を持っていたり、信者が他宗教への改宗を禁じている場合、パートナーの信仰を受け入れることが非常に困難になります。たとえば、仏壇の設置や日々の祈りといった日常的な信仰行為について、どちらかが強い拒否感を示せば、生活そのものに支障が出ることもあるでしょう。
また、子どもが生まれた際に「どちらの宗教で育てるか」という問題が浮上し、それまでの関係が一気に悪化することもあります。お互いの宗教観を尊重し合うことが難しいと判断されれば、結婚自体を断念せざるを得ないという選択に直面することもあるのです。
婚約者や家族の反対による破談
実際には、当人同士が宗教の違いを受け入れていたとしても、婚約者の両親や兄弟姉妹、親族が強く反対するというケースも珍しくありません。宗教に対して強い不信感や偏見を持っている家族であれば、過去のトラブルや団体のイメージを理由に、結婚そのものを否定されることがあります。
また、親がすでに同じ宗教に対して苦い経験をしていた場合、たとえ当人がその宗教活動をしていなかったとしても、「信者である」という事実だけで強く拒絶されることもあります。このような場合、話し合いでは解決できず、感情的な対立が長期化してしまう恐れがあります。
信仰は極めて個人的な価値観の問題であるからこそ、結婚という人生の転機において、相手と自分、そして家族の関係性を慎重に調整することが必要です。次章では、実際にどのような解決策があり、現実的にどのような対応が取られているかを詳しく見ていきましょう。
【関連記事】
>婚約者の宗教問題を解決するには?
>創価学会は結婚できないってホント?
>婚約者が創価学会からの脱会を希望している時の対応
結婚したいけど宗教の問題でできない解決策は?
![]()
この章では、宗教の違いが原因で結婚が難しくなっている場合に、どのような現実的な解決策があるのかを解説します。宗教は個人の価値観や生き方に深く関わるものであり、問題を完全に解消することは簡単ではありませんが、相手への理解と柔軟な姿勢によって乗り越えられる可能性は十分にあります。
いずれかの宗教を脱会する
最も分かりやすい解決策のひとつは、自らが所属する宗教を脱会するという選択です。特に、幼少期に親の判断で入会させられた場合や、現在は信仰しておらず、実質的に活動に関与していないようなケースでは、宗教を抜けることに対する精神的な抵抗も比較的少ないことが多いです。
この場合、自身の意思を明確にするために、口頭ではなく書面で正式な脱会通知を送付することが有効です。特に内容証明郵便で通知を送れば、後から「脱会の意思が確認できない」などの主張をされるリスクを防ぐことができ、相手方にも誠実な対応として受け止められやすくなります。
また、相手方の親族や婚約者が宗教に対して不安を持っている場合でも、「信仰を継続するつもりはない」「今後一切の関係を断つ」という姿勢を示すことで、誤解や不信感を払拭できる可能性があります。結婚を真剣に考えるからこそ、過去の宗教的背景にきちんと向き合い、整理しておくことが重要です。
互いの宗教を維持したままで結婚を試みる
脱会が現実的でない、あるいはどちらも自身の信仰を大切にしているという場合は、宗教的な考え方の違いを無理に解消しようとするのではなく、互いを尊重し合うことが大切になります。宗教を持つことそのものは否定されるべきものではありませんし、無理にどちらかが信仰を捨てることで、かえって関係が悪化してしまうこともあります。
このような場合には、宗教に関する話題について結婚前に話し合いの場を持ち、今後どのような距離感で宗教と向き合っていくかをすり合わせておくことが必要です。例えば、将来的に子どもを育てる際にどちらの宗教に従うか、宗教行事にはどのように参加するかなど、事前に方針を決めておくことで、不要なトラブルを避けることができます。
さらに、宗教のことで揉めないよう、婚姻契約とは別に合意書や確認書といった文書を交わしておく方法もあります。これは法的効力を求めるというより、お互いの認識のズレを防ぐ目的で作成するものです。第三者を立てて話し合いをすることで、冷静にお互いの立場を理解し合える機会にもなるでしょう。
いずれの方法を選ぶにせよ、大切なのは宗教の違いを「問題」として排除するのではなく、「違いがあることを前提にどう付き合っていくか」を丁寧に考えていく姿勢です。宗教を理由に別れを選ぶのではなく、信頼関係を築きながら前向きに乗り越えていく道もあるということを、ぜひ覚えておいてください。
結婚後に宗教問題が発覚した場合の円滑な話し合い
![]()
結婚後に宗教の違いが問題となることは、決して珍しいことではありません。入籍前にはあまり宗教について深く話し合う機会がなかった場合や、家族に信仰の強い人物がいる場合など、後になって宗教が関係性に影を落とすこともあります。こうした状況においては、互いの立場や信仰に対する理解と尊重の姿勢が不可欠です。
ここでは、無用な衝突を避け、円満な関係を維持するための話し合いのポイントをご紹介します。
相手の宗教を認める姿勢
結婚生活を続けていく中で、信仰のあり方が違うことがわかった場合でも、まずは相手の信じている価値観を理解しようとする姿勢が大切です。自分にとって馴染みのない宗教や考え方であっても、頭ごなしに否定することは避け、なぜその信仰を大切にしているのか、どのような意味を持っているのかを、じっくりと聞いてみましょう。
信仰の対象や実践内容を完全に受け入れる必要はありませんが、少なくとも否定や非難ではなく、理解と尊重の態度を持つことで、相手も安心し、自分の考えを正直に伝えやすくなります。信仰の背景には、その人の育った環境や親との関係など、複雑な事情があることも多いため、表面的な部分だけで判断しないことが求められます。
冷静に話し合いで解決する姿勢
宗教についての話し合いは、時として感情的な衝突を招く原因になりがちです。特に、相手の宗教に対して強い拒絶感がある場合や、過去に宗教にまつわるトラブルを経験していると、話し合い自体が難しくなることもあります。
そのようなときは、無理に二人だけで結論を出そうとせず、信頼できる共通の知人など、感情に左右されず冷静に話を整理してくれる人に同席してもらうことで、相手の考えを客観的に理解しやすくなります。また、話し合いの内容は記録しておくと、今後のすれ違いを防ぐ手助けにもなります。
話し合いでは、相手に「改宗を求める」「活動をやめさせる」といった要求ではなく、「どこまでが許容できるか」「どうすれば互いに安心して過ごせるか」という具体的な折り合いのポイントを探る視点が重要です。
互いの家族(他宗教の熱心な信者の場合)にはすぐに言わない
相手の家族や自分の親が、強い宗教的信念を持っている場合には、宗教に関する話題を持ち出すタイミングや方法には特に慎重さが求められます。家族が宗教に誇りや使命感を持っている場合、突然「信じたくない」「距離を置きたい」といった話をすると、強く反発されたり、関係が悪化する可能性も否定できません。
そのため、まずは夫婦間で方針や今後の向き合い方をしっかりと話し合い、考えを整理した上で、家族への伝え方を協議するのが望ましいでしょう。宗教の問題は、家庭内での価値観の衝突にもつながるため、当人同士で土台を固めた上で、段階的に家族に説明することが、不要な混乱を防ぐことにつながります。
また、宗教的背景を持つ家族に対して説明を行う場合は、感情的にならず、丁寧かつ冷静な言葉を選ぶよう心がけることが重要です。特に、家族にとって大切な信仰であることを尊重しながら、自分の立場を伝えるバランス感覚が求められます。
【関連記事】
>宗教を辞めたいと考えている2世会員の方へ
>宗教を辞めるのが怖い時はどうすればいいの?
>母親が所属する宗教を辞めさせたい!
結婚後の宗教問題を解決する脱会の方法
![]()
このトピックでは、結婚後に宗教を理由とする不一致や不安が生じた場合に、現実的な対応策として「脱会」を選択する際の具体的な手段について解説します。特に、過去に親の意向などで宗教団体に入会させられた方や、自身の信仰心とは無関係に形式的に登録されていた方にとって、脱会の手続きを円滑かつ明確に進めることは、結婚生活を安定させるためにも極めて重要な意味を持ちます。
内容証明郵便による通知
宗教団体から正式に脱会するためには、単なる口頭での申出や、会員との日常的なやりとりを断つだけでは不十分です。特に、信仰の有無や脱会の意思がはっきりしていない状態では、関係が曖昧なまま残ってしまい、将来的に再び勧誘を受けたり、選挙などの特定の場面で連絡を受けたりする可能性があります。
こうしたトラブルを未然に防ぐために有効なのが、「内容証明郵便」を活用した正式な脱会通知です。これは、いつ・誰が・どのような内容の文書を差し出したのかという事実を、日本郵便を通じて客観的に証明することができる特殊な郵便手段です。受け取った側にも、差出人の意思が文書として記録されるため、感情的な対立を避けつつ、脱会の意思を明確に示すことができます。
また、宗教団体によっては、組織内で脱会届の手続きを定めている場合もありますが、その方法では本人の意思がきちんと記録として残らなかったり、支部・担当者により処理が滞ることもあるため、外部に証明力のある方法を用いることが必要不可欠です。
内容証明郵便による脱会のメリット3つ
婚約者やその家族に対する誠意の証明
宗教による結婚問題が生じた場合、当人同士の話し合いだけでなく、相手の両親や親族からの理解を得ることが非常に大切になります。過去に宗教団体に所属していた履歴がある場合、そのままの状態では相手方から不安を持たれやすく、場合によっては結婚自体に消極的な態度を取られることもあります。
そのため、書面での脱会通知を送付することは、自らの意思を示し、信仰にとらわれない立場であることを明確にする手段になります。これは形式的な手続き以上に、婚約者やその家族に対して信頼と誠実さを伝える一つの行動といえるでしょう。
再勧誘や連絡を法的に拒絶できる
一度関係を断ったつもりでも、宗教団体や会員からの再勧誘が続いてしまうケースは少なくありません。そうした場合でも、内容証明郵便を送っておくことで「これ以上の接触を断る意思表示を明確に行った」証拠となり、仮に再度連絡があった場合は、差出人側に対して警告や法的対応を検討する正当な根拠となります。
また、宗教行事の前後などに繰り返される特定の連絡や訪問を、あらかじめ文書の中で禁止しておくことで、精神的なストレスや生活の平穏が乱されることを避けることにもつながります。
本人の意思を明確に残す証拠となる
脱会の手続きにおいて重要なのは、後から「脱会の申し出がなかった」「処理されていない」といった主張をされないようにすることです。内容証明郵便はその点で極めて有効であり、自分自身の意志を法的に記録として残すことができます。
とくに今後、婚姻や出産、転居などの人生の節目で宗教的な問題が再燃しないようにするためには、現在の段階でしっかりとけじめをつけておくことが望まれます。文書で明確に意思を残すことによって、宗教との関係におけるトラブルの再発防止につながり、平穏な生活環境の確保につながります。
【関連記事】
>宗教をやめるにはどうすればいいの?
>宗教をやめるのは難しいの?
>創価学会への脱会通知を内容証明で送る
宗教問題による契約書や通知書の作成はお任せください
![]()
宗教を理由に結婚をためらっている方や、ご自身または相手方の宗教的背景により家族・親族との関係が複雑になっている方、または結婚を見据えて過去の宗教団体との関係にけじめをつけたいとお考えの方に向けて、当事務所では一人ひとりの状況に寄り添ったサポートを行っております。
当事務所はこれまでに、結婚に関わる宗教的対立や、信仰上の立場の明確化を求めるケースなど、宗教問題に起因する数多くの契約書・脱会通知書の作成支援に対応してまいりました。特に、第三者との信頼関係を築くために必要な脱会通知の作成、将来的なトラブルを予防する合意書の作成などにおいて、多くのご依頼者様から信頼をいただいております。結婚という人生の大きな選択を前に、宗教問題に悩み苦しむ方の支えになりたいという思いから、特に以下のようなお悩みをお持ちの方には、ぜひ一度ご相談いただきたいと考えております。
- 結婚相手の家族に自分の宗教歴を正直に伝える必要があるが、どう説明してよいか分からない
- 婚約者の宗教に合わせるよう求められており、信仰の継続や脱退に関して書面で整理しておきたい
- 親の影響で信者として登録されていた宗教から正式に脱会し、結婚前に自分の立場を明確にしたい
- 宗教に否定的な婚約者の家族に対して、自らの無信仰の立場を証明したい
- 信仰の違いで関係が不安定になっており、互いの合意内容を契約書として形に残しておきたい
- 結婚を機に過去の信仰から距離を置くことを決めたが、宗教団体からの再接触や勧誘が不安
宗教と結婚の問題は非常にデリケートで、個人の人生や人間関係に大きな影響を与えるものです。当事務所では、法律と感情の両面に配慮した柔軟な対応を心がけておりますので、ご自身の信条や人生設計を守るための第一歩として、ぜひ一度ご相談ください。
手続の流れ
1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。
| ⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |
2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。
3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。
4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成しご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)
5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。
6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。
【郵送書類】
・内容証明郵便の謄本 計1通
・配達証明書 計1通
・領収書 計1通
・その他書類(名刺、アンケート等)
以上が大まかな手続の流れでございます。
ご依頼いただくメリット
下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。
メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。
メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。
メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。
メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。
ご依頼料金
| 業務内容 | 案件(受取方) | 基本料金 | 概要 |
| 内容証明郵便の 作成と差出 | 個人・法人 | 33,000円~ | 2,000文字から5,000文字程度の通知書を作成いたします。 |
| 内容証明郵便 トータルサポート | 〃 | 44,000円~ | 〃 |
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。そのため、実施するサービスには自信をもっております。
![]()
内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。
![]()
| 【参考】 >日本郵便株式会社 内容証明 |
結婚したいけど宗教の問題でできない!?-よくある質問
Q.結婚相手の信仰に不安があります。宗教を理由に結婚をやめるのは仕方ないことですか?
A.宗教の違いによって価値観や生活習慣にズレが生じ、結婚に踏み切れないケースは珍しくありません。特に将来子育ての方針や家族の関わり方に影響することが予想される場合は、慎重に検討することが大切です。無理に関係を続けることが双方にとって負担になるなら、やむを得ない選択になることもあります。
Q.婚約者に昔入っていた宗教団体のことを話すべきでしょうか?
A.信頼関係を築くためには、過去の宗教的な経緯を正直に伝えておくことが望ましいです。特に、自分の意思ではなく家族の方針で加入していた場合などは、その背景を丁寧に説明することで、結婚相手の理解を得やすくなります。
Q.宗教が原因で結婚を反対されてしまいました。どうすれば説得できますか?
A.宗教に関する懸念は感情的な反発に発展しやすいので、冷静な対話が重要です。特に、自分が現在は宗教活動に関与していないことや、将来関わる意志がないことを具体的に伝えると、安心感につながる場合があります。また、書面による脱会などの行動を示すことで、真剣な姿勢が伝わりやすくなります。
Q.宗教問題で家族に反対されている相手と、どうしても結婚したいのですが方法はありますか?
A.家族の理解を得るためには、宗教を持っている理由やその関わり方を丁寧に説明し、相手が信仰によって他人に迷惑をかけない人物であることを示すのが効果的です。場合によっては第三者を交えた話し合いをするのも一つの方法です。
Q.宗教団体をやめたことを証明する方法はありますか?
A.はい、あります。たとえば「脱会通知書」を内容証明郵便で送付することで、脱会の意思表示を記録として残すことができます。これにより、将来的な誤解やトラブルを防ぐ証拠となります。
Q.自分はもう信仰していないのに、婚約者の家族が「まだ信者ではないか」と疑ってきます。どう対応すれば?
A.まずは誤解を解くことが大切です。たとえば「現在は一切関与していない」「団体とは距離を置いている」ということを具体的に伝え、できれば脱会を証明する書面などを見せることで、不信感を和らげることができます。
Q.宗教を脱会したいけど、家族が反対していて動けません。どうすれば?
A.宗教問題に家族が関わっている場合は、慎重な対応が求められます。まずは自分の意思を固め、できるだけ対立を避けながらも、第三者(専門家など)を通して手続きを進める方法もあります。脱会は「信教の自由」として保障された権利です。
Q.結婚してから相手が熱心な宗教の信者だとわかりました。離婚の原因になりますか?
A.宗教活動が生活に支障をきたすレベルであり、かつ相手が協議に応じない場合は、民法上の離婚原因に該当すると判断される可能性があります。ただし、すぐに離婚に進むのではなく、まずは話し合いや夫婦カウンセリングなどを検討するのが望ましいです。
Q.結婚後に宗教の問題を防ぐための方法はありますか?
A.宗教に関する取り決めを書面にまとめておく方法があります。たとえば、「子どもの教育方針」「宗教行事への参加」「信者との距離のとり方」などをあらかじめ合意書として残しておけば、誤解や衝突を回避しやすくなります。
Q.結婚と宗教問題について、行政書士にできることはありますか?
A.行政書士は、脱会通知書や合意書などの文書作成を通じて、信仰に関する整理や家庭内トラブルの予防をサポートすることができます。中立的な立場で書面にすることで、感情的なやり取りを避け、冷静な解決を目指すことが可能です。
結婚したいけど宗教の問題でできない!?-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、結婚したいけど宗教問題でできないとお悩みの方に向けて解決方法や話し合いのポイントなどについて述べさせていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。
1.宗教によって結婚が困難になる現実とは
信条の不一致は、将来を見据えた生活のなかで大きな価値観の相違をもたらすことがあります。教義の対立や生活様式の違いにより、同居すら困難になる例も存在します。さらに、子育て方針に宗教的観点が加わることで関係が悪化することもあります。
本人同士は理解し合っていても、親族から強い反対を受けることも少なくありません。信仰に対する過去の体験や偏見に基づき、受け入れを拒まれる事態もあります。このような事情から、宗教的背景は感情面だけでなく、家庭内での調和にも影響を及ぼす要素となります。
2.信仰の違いによる障害を乗り越えるには
信条の不一致が障害となっている場合、対応策はいくつか考えられます。その一つが、宗教団体から正式に離脱するという方法です。特に、自分の意思ではなく親の判断で登録されていたケースでは、精神的負担も比較的少なく、現実的な選択肢となります。
正式に意思を示すには、口頭ではなく書面による通知が有効です。配達の履歴と内容が記録に残る方法で送れば、後日トラブルとなるのを防ぐことができます。
一方、互いの信仰を尊重し合いながら婚姻関係を築く方法もあります。この場合は、家庭内で宗教にどう向き合うかを事前に話し合い、必要に応じて合意書などを交わすことで、意識の食い違いを抑える工夫が必要となります。
重要なのは、信仰の違いを否定するのではなく、どう共存するかを丁寧に検討する姿勢です。
3.婚姻後に宗教問題が表面化したときの対応
結婚生活が始まってから、宗教にまつわる摩擦が生じることもあります。信仰の存在を知るのが遅れたり、配偶者の親族に強い信者がいたりすることで、後から問題が浮上することもあるのです。
その際はまず、相手が信じている価値観を受け入れる姿勢が求められます。すぐに否定せず、信仰の背景にある考え方や生き方に耳を傾けることが、信頼関係の維持に繋がります。
対話を通じて落ち着いて方向性を決めることが大切であり、感情的なぶつかり合いを避けるために第三者の立ち会いを取り入れることも一案です。
また、相手の親族が信仰に積極的である場合、説明のタイミングや方法には細心の注意を払う必要があります。いきなり突きつけるのではなく、あらかじめ夫婦間で十分にすり合わせたうえで伝えることが、無用な混乱を避ける鍵となります。
4.結婚後の不安を解消するための脱会手続き
過去に親の意向で団体に登録されたが、現在は信仰心がないという方は、自分自身の立場を整理するためにも正式な退会手続きを検討する価値があります。
その際には、郵便によって手続きの証拠が残る方法が効果的です。書類を送付した事実が証明されれば、今後の関係遮断やトラブル回避に役立ちます。
また、婚約者や親族に対しても、自分が信仰と距離を置いていることを明確に伝える手段となり、相手への信頼性を高める効果もあります。
信仰を理由とした干渉や再びの勧誘を避けたい場合にも、書面による通知は有効です。特定の行為をやめてほしい旨を明記しておけば、繰り返しの接触があった際の対処にも役立ちます。
本人の意思を明確に記録に残すことで、過去の関係が将来の生活に影を落とさないようにするための、重要な手続きと言えるでしょう。